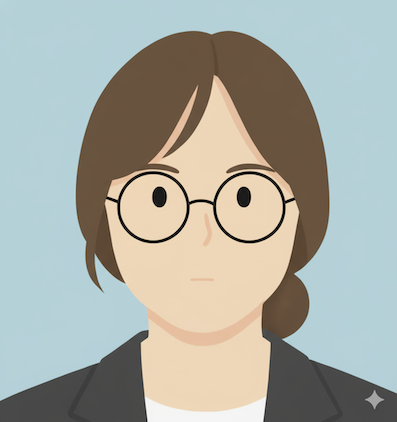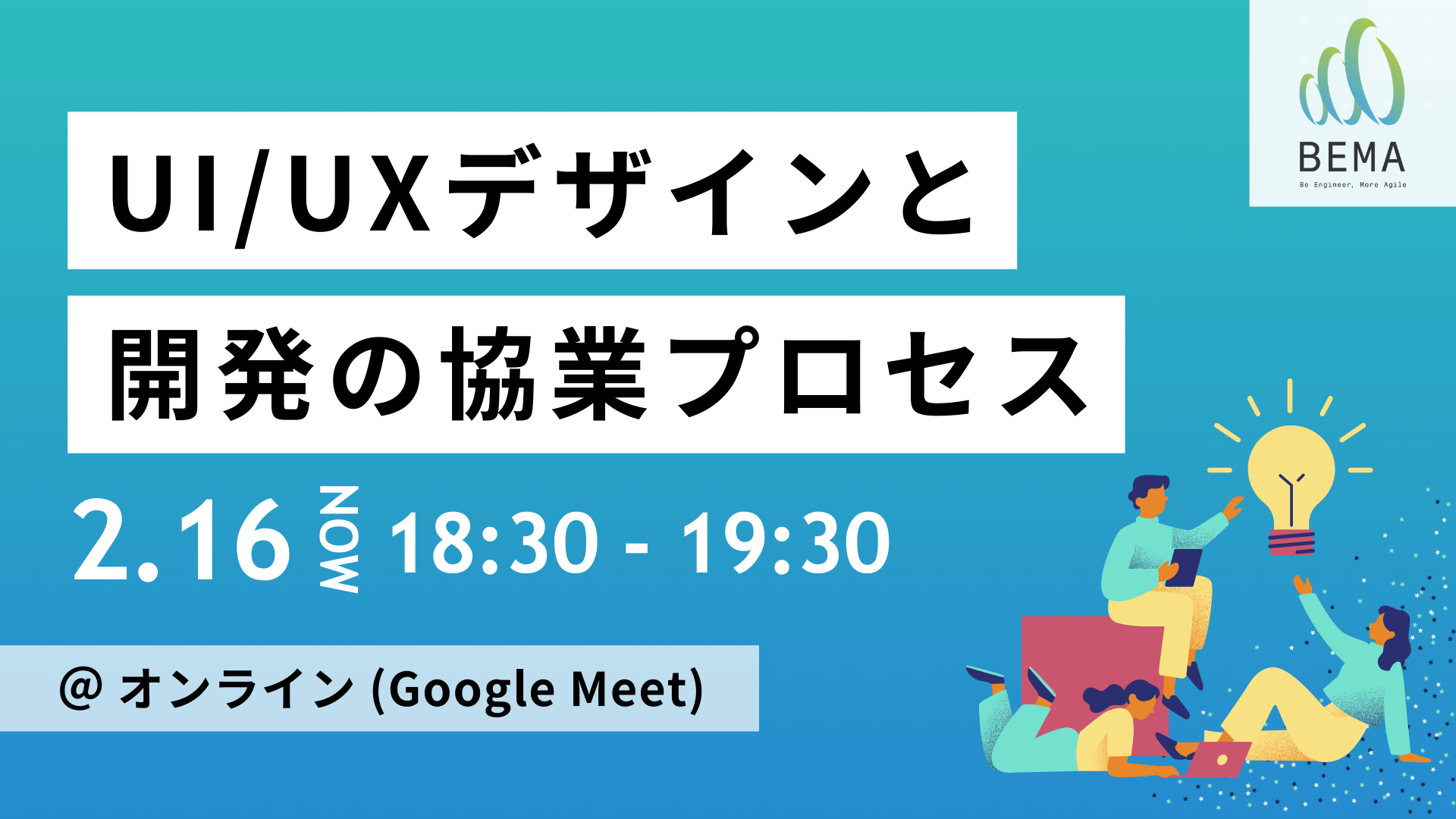TerraformとAnsibleで生成AI基盤のインフラを自動化する方法
はじめに
生成AIの進化に伴い、インフラの構築・管理の自動化はますます重要な課題となっています。特に、Infrastructure as Code(IaC)を活用することで、手作業の削減・エラーの防止・管理の最適化が可能になります。私たち生成AI基盤チームでは、Dify を用いたインフラ構築を行っていますが、さらなる運用効率化と管理コストの削減を目指し、Terraform と Ansible を活用したインフラ自動化に取り組んでいます。本記事では、IaC導入の背景、使用ツールの選定理由、運用上の課題とその解決策を解説し、IaCの導入を検討しているエンジニアや、Terraform/Ansibleの活用を学びたい方に向けた方法をお届けします。
今後、実際の自動化の手順や、導入時に直面した課題・解決策についても公開していく予定です。
背景
私が生成AI基盤チームに参加した際、ハンズオンの内容が自動化と手動実行が半分ずつで構成されていました。このため、プロセスが非常に複雑に感じました。また、makeファイル(ビルドやテストを自動化するためのツール)を使った自動化が行われていたため、後のインフラの状態を示す「ステートファイル」との関連性が薄かったのです。この経験から、過去に使用したIaCツールを活用して、インフラの構築を強化することを決めました。
インフラコード化のツール選定
採用したツールはTerraformとAnsible
私は、インフラのコード化に「Terraform」と「Ansible」という2つのツールを選定しました。以下にそれぞれのツールの特徴と選定理由を表で示した後で、詳しく説明します。
ツール名 | 用途 | 主な特徴 |
Terraform | インフラのプロビジョニング | マルチクラウド対応 / ステート管理 / CI/CD統合/コミュニティの豊富さ |
Ansible | 構成管理・アプリデプロイ | ロールの組み合わせ/YAMLベース / 冪等性 / ロール管理 |
Terraform
Terraformは、インフラをコードとして管理するためのツールです。主な特徴は以下の通りです。
- マルチクラウド対応: Terraformは、AWS(Amazon Web Services)、Azure、Google Cloud Platformなど、複数のクラウドプラットフォームに対応しています。これにより、特定のクラウドプロバイダーに依存することなく、インフラを構築できます。
- ステートファイルの管理: Terraformは、構築したインフラの状態を「ステートファイル」として保存します。これにより、インフラの変更を追跡し、整合性を保つことができます。
- CI/CDとの統合: 最終的にはGitHub Actionsを用いて、Terraformのコードを自動実行する予定です。これにより、コードの変更が自動で反映されるため、デプロイメントプロセスが効率化されます。
- コミュニティとプラグインの豊富さ: Terraformは広く使われているため、コミュニティも活発で、多くのプラグインが用意されています。これにより、さまざまな要件に対する柔軟な対応が可能です。
Ansible
Ansibleは、構成管理やアプリケーションのデプロイメントを自動化するためのツールです。以下の特長があります。
- ロールの組み合わせ: Ansibleでは、異なるタスクを「ロール」として定義し、それらを組み合わせることができます。これにより、複雑な構成管理も簡単に実現できます。
- YAML形式のプレイブック: Ansibleの設定はYAML(人間が読みやすいデータ記述言語)で記述されます。これにより、構成の可読性が高く、他のチームメンバーも理解しやすくなります。
- 冪等性: Ansibleの最大のメリットの一つは「冪等性(べきとうせい)」です。これは、同じ操作を何度実行しても、最終的な結果が変わらないことを意味します。例えば、特定のソフトウェアがインストールされているかどうかを確認し、未インストールであればインストールするという処理を行った場合、すでにインストールされている場合には何も変更しません。これにより、予測可能で安定した運用が可能になります。
- インフラとアプリケーションの分離: Terraformでインフラ部分を構築し、その状態を管理する一方で、Ansibleを使ってアプリケーション部分を管理するというアプローチを取りました。これにより、役割の分担が明確になり、管理が容易になります。
インフラのコード化における課題
インフラのコード化は、多くの利点をもたらしますが、いくつかの課題も存在します。特に、ハンズオンを通じてインフラを学ぶ人々に対して、どのように説明するかが難しいと感じました。
- 知識のギャップ: インフラに不慣れなメンバーが多い中で、複雑な概念をどう説明するかが課題です。具体的な例やシナリオを用いて、段階的に理解を促す必要があります。
- ファイル分割と命名規則: コードを複数のファイルに分割することや、変数の命名規則をどうするかは、チーム内での話し合いが必要です。これらは初めてインフラをコード化する際に特に注意が必要なポイントです。
- 記述方法の統一: チーム全体で記述方法を統一することで、可読性やメンテナンス性を向上させる必要があります。初めての取り組みでは、試行錯誤が避けられないでしょう。
まとめ
生成AI基盤のインフラをIaCで自動化することで、効率的な運用が可能になります。TerraformとAnsibleを活用することで、インフラ管理の透明性と柔軟性が向上しました。今後も継続的にインフラのコード化を進め、チーム全体での知識共有を図っていきたいと思います。これからIaCを始めようとしている方々にとって、この記事が参考になることを願っています。
この記事を書いた人

関連記事
- Azure Functionsへの手動デプロイ:Azure ...
生成AI基盤チーム
- 【Dockerセキュリティ入門】.envファイルの危険性と安...
Tsai Yalin
What is BEMA!?
Be Engineer, More Agile