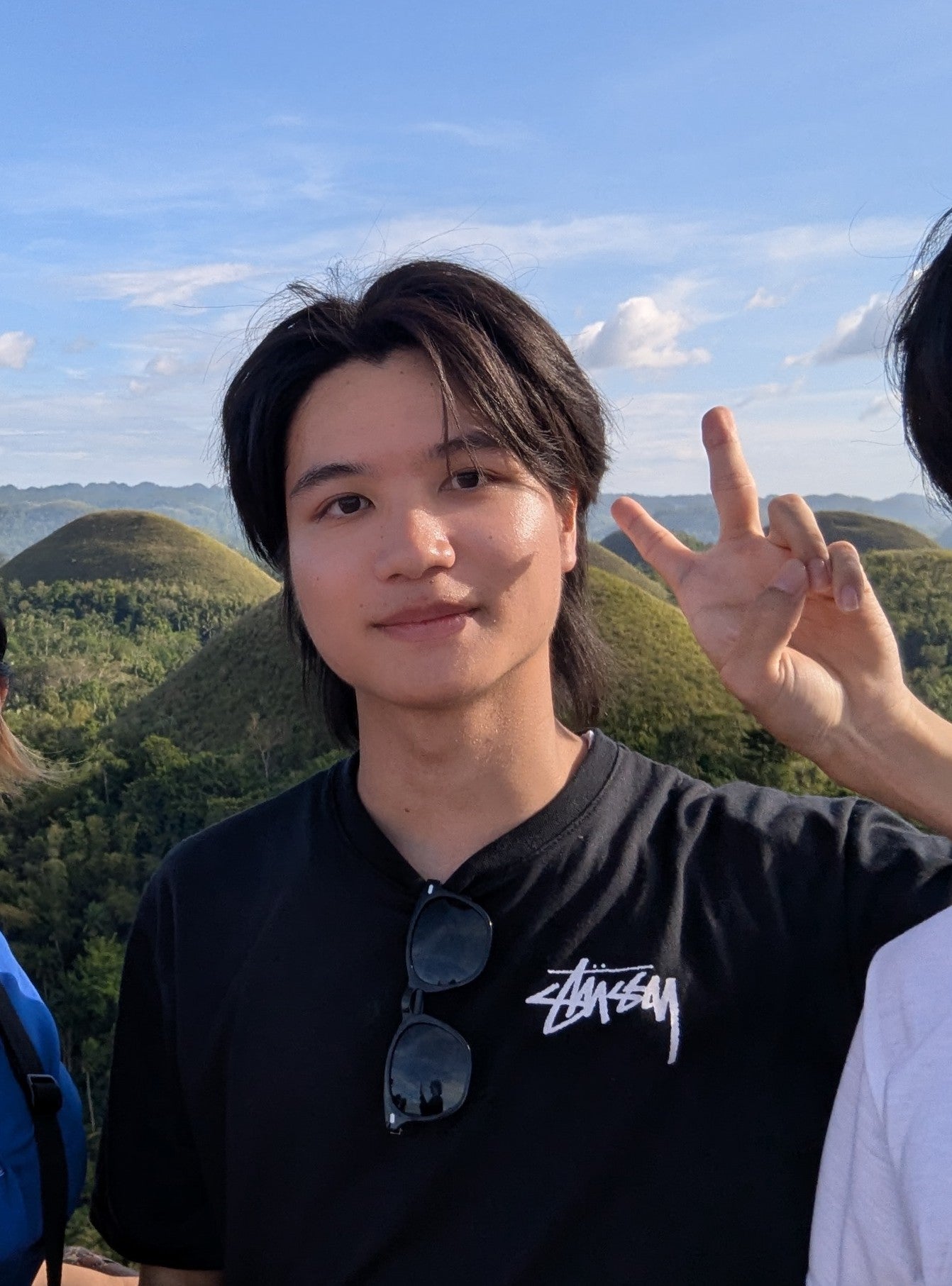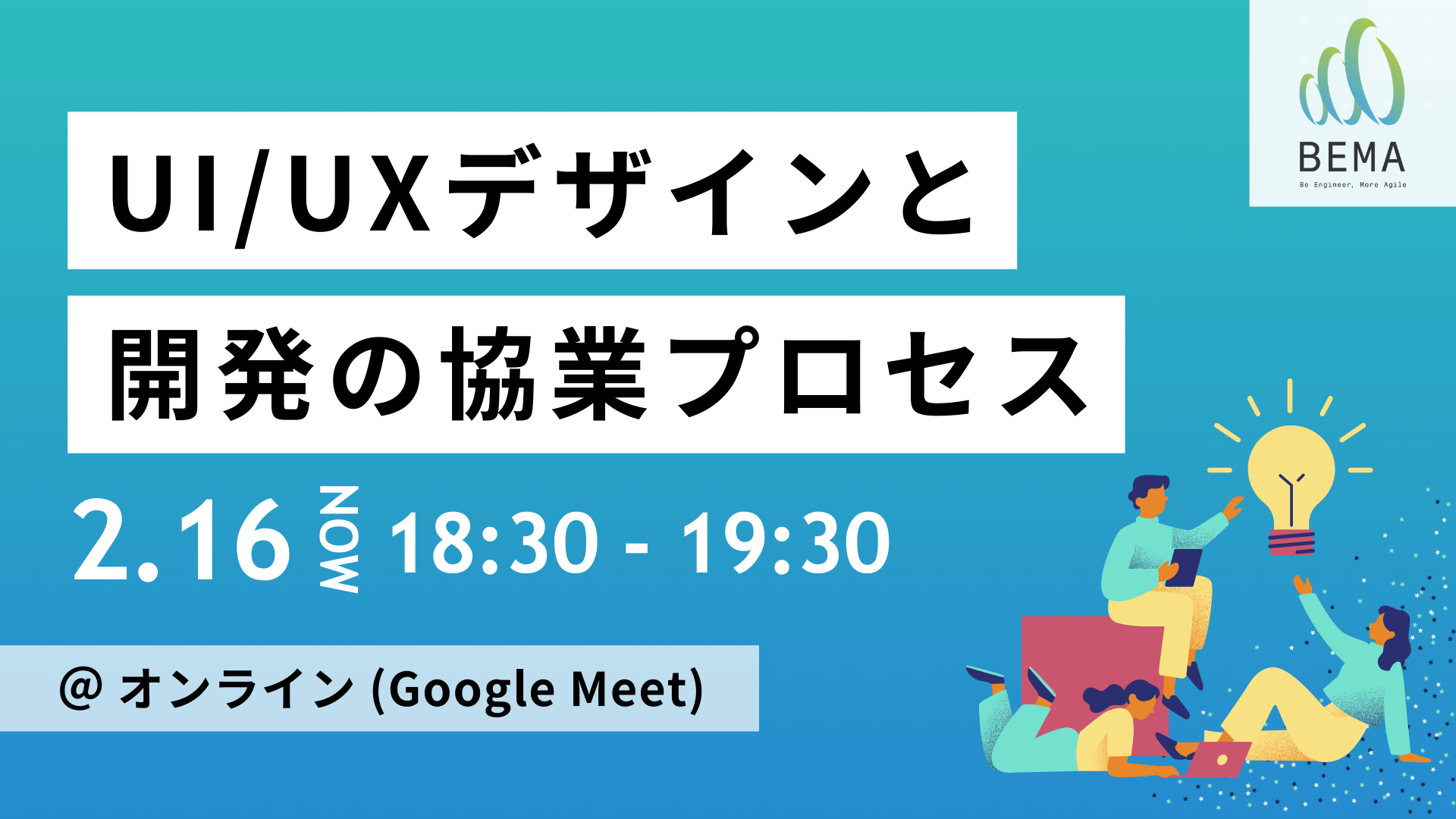【第1回/Google Cloud入門】日本CTO協会主催 新卒エンジニア合同研修潜入レポート
はじめに
先日、日本CTO協会主催の新卒エンジニア合同研修へ参加させていただきました! この合同研修は、業界全体・企業横断で次世代の新卒エンジニアを育てることを目的とした取り組みだそうです。また、他社の同期と横のつながりを深めることも重要な目的の一つとなっています。
全6回開催予定のうち、今回は記念すべき第1回となるグーグル・クラウド・ジャパン合同会社様による研修をレポートします! 今回の研修には、様々な企業から約130名強の新卒エンジニアが参加していました。
Google 渋谷オフィス - 受付
スペシャリストの視点から学ぶ!データ分析とAI/MLの最前線
研修は、Google Cloudのスペシャリストによるセッションからスタートしました。
まずは、データ分析専門のカスタマーエンジニアである山田雄さんが登壇され、データ活用の重要性についてのお話を受けました。日本国内のデータが2010〜20年の平均で、1年間に17兆円もの価値を生み出しているというお話から始まり、データを「より早く、より安全に、より再現性高く」価値に変換することの重要性が語られました。
データ活用基盤の中核として紹介されたのは、BigQueryです。サーバーレス設計により運用負荷を軽減し、ストレージとコンピュートが分離した独自のアーキテクチャ(BorgやJupiterといったGoogle独自の技術が支えているそうです)がスケーラビリティと費用対効果の高さを実現しているとのこと。構造化データだけでなく、非構造化データや、今増加しているリアルタイムデータも扱える柔軟性も大きな特徴です。
特に印象的だったのは、BigQueryとGeminiの連携によってデータ分析が大きく変わってきているというお話です。SQLの生成やデータの前処理、データの検索や可視化を自然言語でできるようになり、エンジニアでなくともデータを扱いやすくなっているそうです。
続いては、Google Cloud Associate Customer Engineer のYi Cheng(伊程)さんがAI/MLの最前線について解説してくださいました。生成AIの活用は、私たちの働き方に大きなインパクトをもたらすとのこと。タスクの時間短縮や質の向上はもちろん、付加価値の高い業務へのシフトや、作業の均質化に繋がるなど、企業の競争力を飛躍的に向上させる可能性を秘めているそうです。
GoogleのAIといえば、やはりGeminiです。テキストだけでなく、音声やコード、画像など、マルチモーダルに対応している点や、200万トークンという長いコンテキストを理解できる点、そしてGoogleプロダクトとの連携が強みとして挙げられました。
また、特定の情報源に基づいて回答する目的特化型AIであるNotebookLMも紹介されました。PDFやドキュメント、音声データや動画など様々な形式のデータをアップロードでき、それを基に要約やブリーフィング、概要生成をしてくれるツールです。情報源が限定されていることにより、ハルシネーションの発生を抑制できる点も、大きな強みとして紹介されました。会議準備や資格勉強など、具体的な活用事例も紹介され、すぐにでも使ってみたくなりました。
今回の研修に参加したメンバーの議事録をソースとしてアップロードし、要約された文章を出力した
AIの力を引き出す「プロンプトエンジニアリング」の重要性
AIを最大限に活用するためには、プロンプトエンジニアリングのスキルが不可欠だと学びました。大規模言語モデル(LLM)は「次の単語を予測する」という処理を行っているからこそ、人間が意図する出力を得るためには、適切な指示を設計する必要があります。
良い指示のポイントとして、人間との共通点と生成AI特有の事項を踏まえることが挙げられました。具体的には、
詳細かつ明確な指示を出す。
AIに役割を与える (ペルソナ指定)。
「Don't」(するな)よりも「Do」(せよ)で指示する。
回答できない場合の代替案を用意しておく。
繰り返し思考し、フィードバックする (一発で完璧を目指さない)。
などが重要なのだそうです。これは、普段のコミュニケーションにも通じるところがあり、とても勉強になりました。
生成AIを「自分ごと」にするワークショップ
セッションの後にグループに分かれてワークショップを行いました。このワークショップの目的は、生成AIツール(Gemini App、 NotebookLMなど)を実際に使い、日々の仕事や学習における活用イメージを掴むことにありました。また、グループワークを通じて他の参加者との交流を深め、様々なロールや業務への理解を深める貴重な機会となりました。
ワークショップでは、新卒エンジニアが実際に直面しそうな課題に対して、生成AIをどう活用できるか具体的なアイデアを創出しました。例えば、
日報作成・復習サポート:日報をNotebookLMに入れて成長ステップを抽出
メール・通知チェック:セマンティックサーチで自分に関係する部分を抽出、要約、文言チェック
サイト制作業務:サイトに載せたい内容をNotebookLMでまとめてサイトコンテンツの叩き台を作成
など、身近な業務への応用アイデアが活発に議論されました。特に、サイト制作に関するワークでは、インタビューの書き起こしを基に、Geminiを使ってサイトの構成案や記事のプロンプトを作成するという具体的な体験ができました。
ワークショップ中の様子
研修を終えて
今回の研修は、最新のデータ分析技術や生成AIの動向を学ぶだけでなく、実際にツールに触れ、その活用方法を考える実践的な機会となりました。特にワークショップでは、様々なバックグラウンドを持つ同期たちとアイデアを出し合い、AIを「自分ごと」として捉え、使いこなすイメージを具体化できました。
日本CTO協会が目指す「次世代のエンジニア育成」と「横のつながり支援」が、セッションでの学びとワークショップでの実践・交流を通じてしっかりと実現されている、素晴らしい研修だと感じました!
最後まで読んでいただきありがとうございました!
次回の取材レポートもぜひご覧ください!
What is BEMA!?
Be Engineer, More Agile