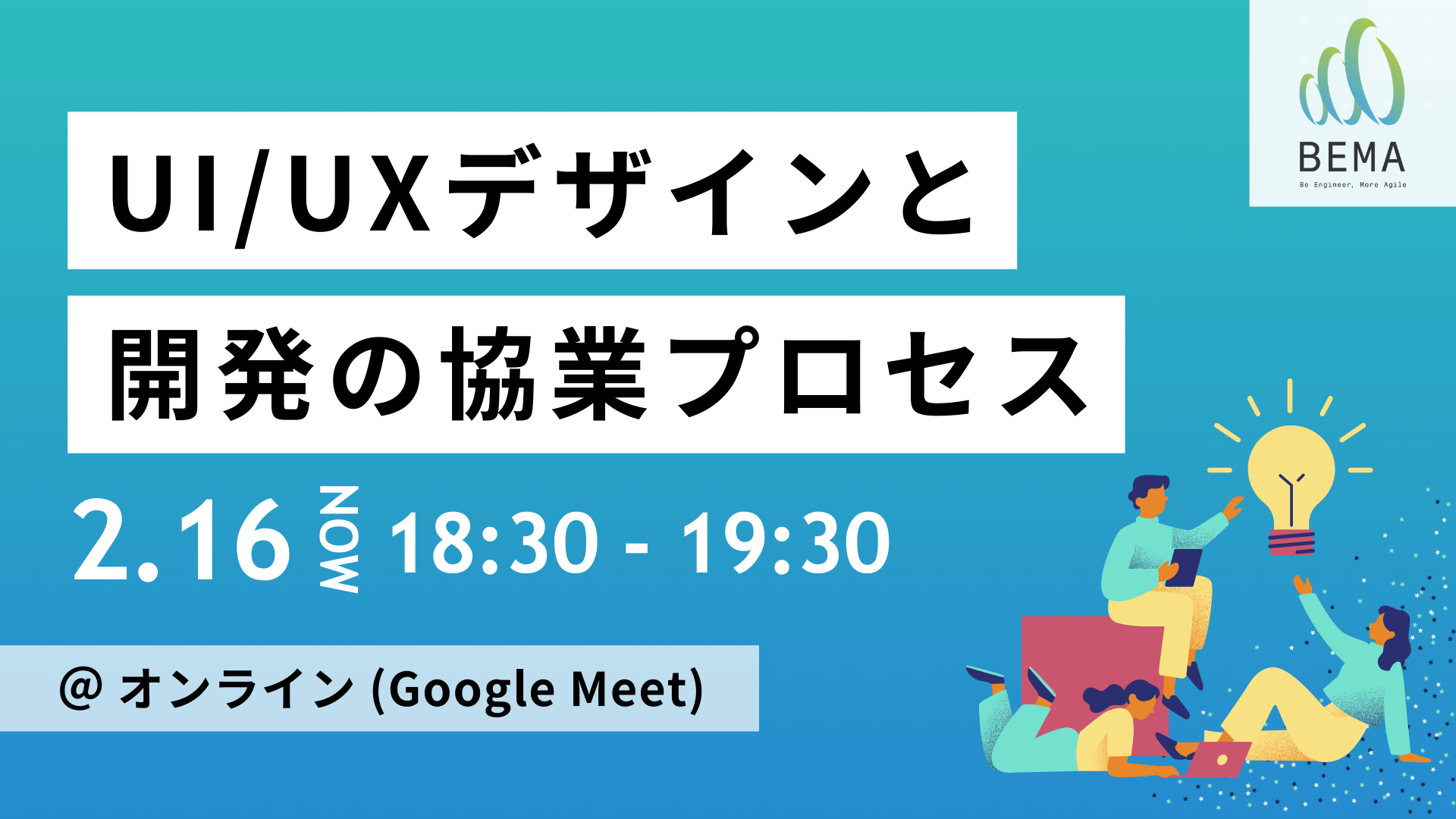ハングリーかつシンプル!インドのエンジニアから私たちが学ぶべきこと
近年、IT大国として世界の注目を集めるインド。なぜ多くのグローバル企業がインドのエンジニアを積極的に採用するのでしょうか? その背景には、彼らが持つ独特の強さがあるからです。
本記事では、筆者が実際に行ったインド視察で得た知見をもとに、インド人エンジニアの強さの秘訣である「ハングリー精神」と「シンプル思考」について解説します。 日本のIT企業の人事担当者やエンジニアの皆様にとって、組織開発や個人のキャリア形成に役立つヒントになれば幸いです!
インド視察の背景
弊社の中長期的な戦略検討のインプットのため、以下の観点からインド視察を実施しました。
デジタルクリエイターの幸せ
エンジニア事業のサービス戦略
海外人材雇用の可能性
なぜインドの視察を選んだのか?
GAFAMなどの巨大IT企業への人材輩出が目覚ましい
高度な技術を持つ優秀な人材を生み出す教育制度がある
顧客企業において、インドへの開発拠点設立や現地採用が増加している
知っておきたい、インドの基本情報
インドについてより深く理解するために、基本的な情報を確認しておきましょう。
人口 | 約14億人(世界1位、2050年には17億人に達するとの予測) |
GDP | 世界5位(近いうちに日本を抜くとの予測) |
時差 | 日本より3時間30分 |
気候 | 雨季と乾季がある |
食文化 | カレー、チャパティー、ビリヤニなどが一般的。ベジタリアン向けメニューも豊富。 |
ハイデラバードのホテルの朝食
インドビザ申請の注意点:招聘状と写真
インドに観光以外で渡航するには、専用のビザが必要になり、そのビザを発行するには招聘状というものが必要になってきます。招聘状はインドに籍のある企業から発行していただきます。その招聘状を元にビザを作成するのですが、そのビザに添付する写真も別途必要になります。大きなカメラ屋に行き、「インドビザ用写真を撮りたい」といえば、仕様はわかっているので、スムーズに撮影してくれます。
ちなみに、白背景なんですが、私が撮影に行ったときは、何を思ったのか、フード付きの白いパーカーを着ていってしまい、店員さんを困惑させてしまいました...みなさん、くれぐれもご注意ください!
とりあえずそのまま出してみて、NGだったら撮り直してくれるってことだったので、そのまま出したんですが、特に指摘なくビザが発行されたので、なんとかセーフでした。白といいつつ生成りだったので、多分大丈夫だったんですね。(たぶん)
視察日程について
期間
2025/2/10(月) 〜 2/16(日) 5泊7日
行程・訪問都市
2/10 (月) | 羽田 ー✈️ー ニューデリー(Transit) ー✈️ー ハイデラバード |
2/11 (火) | ハイデラバード ー✈️ー バンガロール |
2/12 (水) - 13 (木) | バンガロール |
2/14 (金) | バンガロール ー✈️ー チェンナイ |
2/15 (土) - 16 (日) | チェンナイ ー✈️ー ニューデリー(Transit) ー✈️ー 羽田 |
都市の位置関係と距離をイメージしてもらうためのマップ
いわゆる南インド地方中心の視察になりました。それぞれ特徴のある都市で、非常に興味深い示唆を得られたと感じています。
訪問都市と視察先について
また別途それぞれの訪問の詳細はスピンアウトで記事にする予定ですが、まずは上記の日程を踏まえての視察先は以下のとおりです。
【1月31日|オンライン(日本)】
・視察先①:IIT-H 日本人教授※2月11日に訪問予定でしたが、ご都合が合わず、別日にて渡航前にオンラインでインタビューさせていただきました。
【2月11日|ハイデラバード】
・視察先①:インキュベーションセンター
・視察先②:IIT-Hにて学生とランチ
・視察先③:IIT-H内の日本企業
・視察先④:IIT-H内 インキュベーション
・視察先⑤:IIT-H内 就職支援課
【2月12日|ベンガルール】
・視察先①:コワーキングスペース
・視察先②:日本向けオフショア企業
・視察先③:日本企業GCC
・視察先④:インキュベーションセンター
【2月13日|ベンガルール】
・視察先①:団体
・視察先②:日本企業インド法人
【2月14日|チェンナイ】
・視察先①:日本企業インド法人GCC
* IIT-H=インド工科大学ハイデラバード校
* GCC=グローバルケイパビリティセンター
少し前置きが長くなってしまいましたが、インド視察を経てわかったこと、感じたことについて書いていきます。
なぜ、インドのエンジニアは優秀と言われるのか?
インド視察を通して強く感じたことの一つに、「なぜ、インドのエンジニアは優秀と言われるのか?」という問いへの興味があります。IT大国として世界を牽引するインドのエンジニアの卓越性には、いくつかの背景があるようです。
幼い頃からのキャリア意識
まず、彼らのキャリアパス形成の初期段階に特徴があります。「医者か、エンジニアになれ」 と、生まれた時から親に言われる言葉があるほど、社会的に尊敬され安定した職業として、幼い頃からエンジニアという道が有力な選択肢として意識されています。身分制度に囚われず、裕福になることができるという現実的な側面も、この傾向を後押ししていると考えられます。実際にインド工科大学(IIT)の学生とのランチで「なぜエンジニアを目指しているのか」と尋ねた際にも、親や兄弟親戚からの強い勧めがあったという声がありました。
熾烈な教育競争と高い基礎学力
このような背景から、インドでは熾烈な教育競争が繰り広げられます。14億人を超える人口の中で、限られたトップ大学の座を巡って激しい競争を勝ち抜いてきたエンジニアは、必然的に高い基礎学力と、その競争を生き抜くためのハングリー精神を身につけています。インドは国を挙げてIT・理数系の教育を推進しており、高度なエンジニアを養成するための理数系大学が多数設立されています。中でもインド工科大学(IIT)は最難関として知られ、合格率はわずか1%という狭き門です。このようなトップ大学の存在が、理数系教育のレベルを高め、優秀な人材を輩出する基盤となっています。
グローバルな活躍の機会と英語力
また、世界を舞台に活躍する先駆者の存在も、若い世代のエンジニアにとって大きなモチベーションとなっています。GAFAMに代表される世界のビッグテック系企業への人材輩出が目覚ましい状況は、インドのエンジニアがグローバルな舞台で活躍できることを示しています。さらに、公用語が英語であることも、彼らが世界で活躍するための大きなアドバンテージとなっています。
シンプルに探求する思考
日本と比較すると、インドのエンジニアの思考にはシンプルに探求する傾向があるように感じられました。経済が右肩上がりで、街の暮らしも発展していく中で、彼らはやるべきこと、自分にとって最大のプラスだと考えていることに集中し、難しく考えずに、行きたいところへ最短距離で辿り着こうとしているように見えました。
一生懸命学んだことが、理数系大学への入学ということでひとつの成果として評価され、またそれが次の学びへの原資になり、より高みを目指して学び続けるというサイクルをハイレベルでハードに行っているからこそ、彼らはシンプルに成長・スキルアップについて捉え、ハングリーに学び続けることができるのだと考えられます。
このように、インドのエンジニアが「優秀」と言われる背景には、幼い頃からのキャリア意識、激しい教育競争と基礎学力、理数系教育の重視とトップ大学の存在、グローバルな活躍の機会と英語力、そしてシンプルさを追求する思考といった複合的な要因が絡み合っていると言えるでしょう。
優秀なエンジニアはいかに育つのか?その育成の秘訣
インドで「優秀」と言われるエンジニアたちが、さらに高いレベルへと成長していく背景には、いくつかの重要な要素が深く関わっています。
まず、彼らには優秀な人材がさらにハードに学ぶという強い成長志向があります。インド工科大学(IIT)の学生との意見交換では、競争の激しい環境でスキルを磨き、それを発揮して評価され、さらに学び続けるという循環的なシステムの中で、常に高みを目指す姿勢が強く感じられました。このような環境と、切磋琢磨し助け合える仲間(組織)の存在が、彼らの成長を力強く後押ししていると考えられます。
次に、社会全体(産官学)でイノベーションを育む活発なエコシステムの存在が挙げられます。視察で訪れたハイデラバードのインキュベーションセンターは、州政府、学術機関、民間セクターのパートナーシップに基づいて運営されており、まさに産官学連携の象徴と言えるでしょう。ここでは、イノベーションを起こすための仕組みが構築され、グローバルケイパビリティセンター(GCC)の多くが進出するなど、州政府がビジネスフレンドリーで企業誘致を積極的に行っている様子が窺えました。
このエコシステムを支える重要な要素の一つが、スタートアップ投資とオープンイノベーションの活況です。インキュベーションセンターでは、実際にベンチャーを立ち上げようとしている人々からプレゼンテーションを受ける機会があり、彼らの革新的なアイデアと取り組みに触れることができました。大学や州政府が主導してグローバル企業を呼び込み、Deep TechやAI分野を中心に日本企業も積極的に連携し、起業家とイノベーションを生み出す取り組みが行われています。
さらに、インドではビジネスの現場で実際に存在する課題が大学に持ち込まれ、その解決策を学生たちが担うという連携が活発に行われています。IIT-Hでは、企業がビジネス課題を大学に投げかけ、学生たちが先進技術を活用して解決策を見出すといった事例が多く見られるようです。
そして、早い段階からグローバル市場への意識が高いことも、インドのエンジニアの育成における重要な特徴です。公用語が英語であるという点も、彼らがグローバル市場で活躍するための大きなアドバンテージとなっています。
IIT-Hの学生の中には、GoogleやMicrosoftといったグローバル企業から内定を得ているにも関わらず、あえて日本の中小企業を選んだというケースもありました。ただただグローバル企業に就職するステータスを選ぶのではなく、彼らが自分たちが培った技術を存分に発揮し、それを正当に評価され、自身がその会社に貢献し、やりがいのある場所を求めているのだと感じました。
インドのエンジニア(クリエイター)は幸せなのか?
これらを踏まえて、インドのエンジニア(クリエイター)は幸せに見えたのでしょうか?敷かれたレール、激しい競争、高待遇などの競争社会の縮図とも捉えられるような場面もありました。しかし、出会った人たちは、目を輝かせて、活気に溢れていました。
IIT学生との写真
敷かれたレールの中でも、自分たちで未来を選び、作っていける楽しさ、喜びを感じました。
激しい競争社会の中でも、仲間との切磋琢磨、チームワーク、コミュニティがあり、孤独な戦いではなく、より高め合えるいい意味でのライバルだったり、仲間の存在が大きいと感じました。また、それらを下支えするエコシステムや会社の取り組みがあり良いサイクルで回っていると感じました。
高待遇でのステータスも、会社への貢献への適切な評価、それらのキャリア形成するためのやりがいを感じました。競争社会の中でもそういった側面があるため、よりハングリーにハードに突き進めるのだと考えます。
私はその時代を直接知りませんが、日本の高度成長期に似たものがあるのかもしれません。
訪問させていただいた企業様とのランチ
さいごに
今回のインド視察を通して、現地のエンジニアは厳しい競争の中でも未来を創造する意欲とチームワーク、正当な評価と成長に幸せを感じているようでした。
日本のエンジニアにとって、インドのエンジニアの“シンプルな成長志向”は学ぶべき点が多いと感じました。また、組織(会社)としてそれらを活かせる(活かし続ける)組織づくりは継続して必要だと改めて感じました。
最後まで読んでいただきありがとうございます。
後半はお堅い内容になってしまったかと思いますが、視察の道中記は別途公開しますので、ご期待ください!!🔋⚡️💪
この記事を書いた人

What is BEMA!?
Be Engineer, More Agile