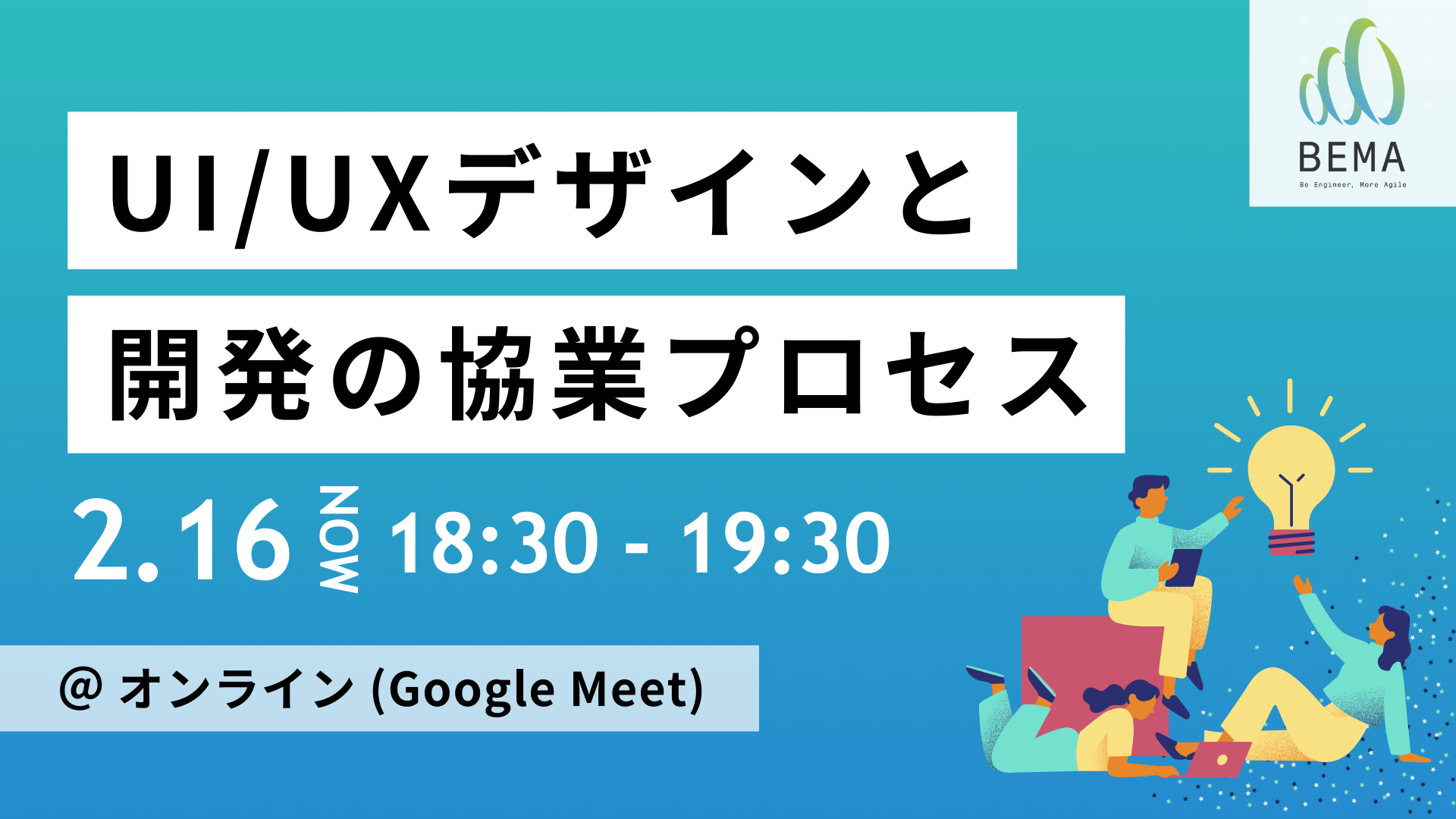マネジメントのモヤモヤを解消!『両利きのプロジェクトマネジメント』に学ぶチームで進める秘訣
はじめに
本記事おすすめの読者
チームの進捗確認やタスクの割り振り、後輩のフォローなど、マネジメントっぽい仕事がじわじわ増えてきた
「リーダーシップって結局何をすればいいの?」「今のやりかたであってるのかな?」と悩んでいる
技術を極めるか、マネジメントの道に進むか、キャリアの分岐点で迷っている
こんにちは、PMOとしてプロジェクト推進やチーム支援に関わっている平光です。
私はエンジニア出身ではありませんが、開発チームと協力しながらプロジェクトの伴走をするなかで、「マネジメントって何をどうしたらいいの?」と迷う瞬間に、何度も立ち会ってきました。
今日は、そんな悩みに向き合うヒントとして、株式会社コパイロツト 米山知宏さんの著書『両利きのプロジェクトマネジメント』を紹介しながら、「ひとりで抱え込まず、チーム全体でプロジェクトを進めるための考え方」をご紹介します。
「最近マネジメントっぽい仕事が増えてきたな」
そんなふうに感じたことはありませんか?
チームの進捗を見たり、メンバーにタスクをふったり、課題整理やプロジェクトの推進のような役割を担っていませんか?
ふと気づけば、自分の仕事が「コードを書くこと」だけじゃなくなっていたりしませんか?
でもそれが、自分に本当に向いているのかと言われると、正直よくわからない。
判断の基準もあいまいで、なんとなくモヤモヤする。
モヤモヤの正体は、本気(ガチ)の証
モヤモヤの感覚って実はマネジメントという役割に本気で向き合っているからこそ生まれるものなんです。
そして「プロジェクトマネジメントって、なんとなく苦手意識があるんですよね」 そんな声をよく耳にします。
特に、現場でずっと開発をやってきたエンジニアの方ほど比較的安定的で手順がある程度決まった環境から、あいまいで先行きが見通しづらい環境に変わるとそう感じる場面が多いように思います。
なぜ、そう感じるのでしょうか?
理由のひとつは、いまのプロジェクトが複雑すぎて正解がひとつじゃないからです。
たとえば
• 仕様変更でスケジュールが一気に崩れる
• 細かく指示を出したつもりが、相手にはプレッシャーとして伝わってしまっていた
• チーム全体のためと思って動いたはずなのに、特定のメンバーの負荷が増加していた
何かを進める時に何かを決めると、それに関連して他のいろいろなことを調整する必要があります。
そして最近では、プロジェクトマネージャーという肩書きがなくても、リーダー的な役割が自然と求められる機会が増えています。
でも、自分の判断に自信が持てず悩んでしまう。
「自分にリーダーなんて務まるのかな」
「この進め方でいいのか、誰にも聞けない」
「なんだか誰かを置き去りにしている気がする」
そんなふうに、「自分やりかたって正しいのかな?」と不安になるのは、経験が浅いからではなく、ちゃんと向き合っているからこそ生まれる悩みなのだと思います。
あのとき、私は全部自分でやろうとしていた
少し私の話をさせてください。
あるプロジェクトで、チームの進行役を任されたとき、納期は迫っていて仕様はあいまい。
「とにかく自分がしっかりコントロールしないと」と必死でした。
そして気づけば全部を自分で抱え込んでしまっていて、会議のファシリテーション、画面共有、メモ取り、進捗確認など全部ひとりで抱えていたんです。
そんなときに出会ったのが、米山知宏さんの言葉でした。
「プロジェクトは、ひとりで回すものではなく、チームでつくるもの」
「自分ひとりで抱えなくていい」
この一言に、肩の荷がふっと軽くなる感覚を覚えました。
リーダーは、ひとりじゃなくていい
本書で印象的だったもうひとつの考え方は、
「リーダーシップはひとりで背負うものではない」という視点です。
リーダーというと、どうしても「先頭でみんなを引っ張る存在」とイメージしがちですよね。
でも、それって実際のプロジェクトでは無理があることも多い。
本書では『関係性の中でリーダーシップは生まれる』という考え方が紹介されています。
• 会議でファシリテーションを担う人
• 課題を先に気づいて言葉にしてくれる人
• 自身の専門分野で軸や方針をつくってくれる人
こうしたちょっとしたリーダーシップを、チームの誰もが自然に発揮できる状態をつくることが大切なのだといいます。
そうすることで、プロジェクトには余白や創造性が生まれ、全員が少しずつリードする場面が生まれます。
これこそが「みんなで育てるプロジェクト」なんです。
マネジメントは「抱えすぎない」のがコツ
実は、私たちが取り組んでいる「PMO育成プログラム」の設計にも、コパイロツトさんに協力していただいています。
コパイロツトさんと週1回で改善ミーティングを行うなかで、ファシリテーションや対話、チームの自律性について、さまざまなことを学ばせてもらいました。
そのなかで繰り返し言われたのが、やはりこの言葉です。
「ひとりで頑張らなくていい」
チームを信じること。
相手に推測で気を遣うのではなく、ちゃんと相手に聞いてみること。
仕組みで回せるところは仕組みに任せて、自分が抱えすぎないこと。
マネジメントって、こういう視点の積み重ねなのだと気づかされました。
最後に:まずどこから始めてみる?
「自分はマネジメント向きじゃないかも」と思っている人にこそ、読んでみてほしいです。
本書には、この記事で紹介しきれなかった具体的なノウハウや実践ヒントがたくさん詰まっているので、きっとちょっとだけ心が軽くなるはずです。
まずは、週に1回、10分でもいいので「立ち止まって話す時間」をチームに持ってみる。
「今どう思っていますか?」と誰かに聞いてみる。
そんな小さな一歩から、チームの空気は少しずつ変わっていきますよ。
📘 『両利きのプロジェクトマネジメント 結果を出しながらメンバーが主体性を取り戻す技術』
著者:米山知宏(株式会社コパイロツト)
▼セミナー開催のお知らせ▼
▼メンバーズPMO支援サービスのご紹介▼
この記事を書いた人
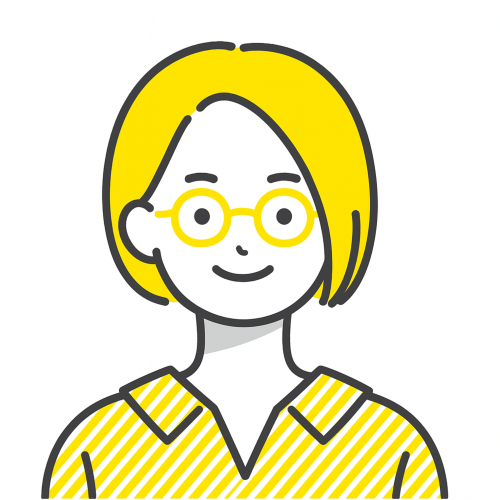
What is BEMA!?
Be Engineer, More Agile