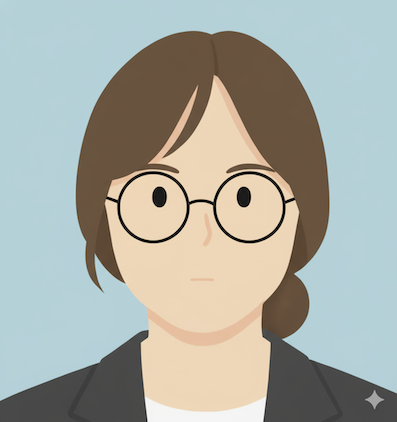NotebookLMで社長の思考をAI化してみた話 〜エンジニアの目標設定と評価面談を変える自己成長ハック〜
こんにちは、生成AI基盤チームの兼子です。
評価面談や目標設定にモヤモヤを感じている若手エンジニアの皆さんへ。
今回は、エンジニアの皆さんが直面する目標や評価面談について、私がやってみたことをまとめて共有できればと思います。
はじめに:AIで上司の思考をハックし、キャリアを加速させる
半年に一度の目標設定面談。多くのエンジニアが、日々の業務と会社のビジョンをどう結びつけるか、頭を悩ませているのではないでしょうか。私もその一人です。
株式会社メンバーズ デブオプスリードカンパニーのエンジニアとして、デブオプスリードカンパニー社長(廣石さん)がnoteで発信する哲学
を深く理解し、自分の目標に落とし込みたいと常々考えていました。
私たちの会社には、単に作業をこなすだけでなく、その仕事の「なぜ」を常に問い、自律的に学ぶことを奨励する文化があります 。
そこで、AIエンジニアとしてのスキルを自分自身のために使う、ある実験を思いつきました。「カンパニー社長の思考をソースにしたAI、いわば『カンパニー社長AI』を構築し、キャリアの羅針盤にできないか?」この記事は、その個人的な実験から生まれた、AIを活用した新しい自己成長のアプローチです。
実験のツール:なぜNotebookLMだったのか
この実験の成功には、適切なツール選びが不可欠でした。私が選んだのは、Googleが提供するAIツール、「NotebookLM」です。
その理由は、NotebookLMの特徴の一つとして、ユーザーが提供した情報源(ソース)にのみ基づいて回答を生成する「ソースグラウンデッド」なツールだからです 。これにより、AIがインターネットの不確かな情報を元に「幻覚(ハルシネーション)」を起こすことを防ぎ、すべての回答をカンパニー社長自身の言葉に根拠づけることができます。
また、NotebookLMの強みとして、あらゆるデータソースを取り込むことができるので、今後いろいろなメディアに公開されたデータを取り込んで精度を上げることができる点でも優れていると感じました。
さらに、回答には必ず引用元が明記され 、クリック一つで原文を確認できるため、解釈の妥当性を常に検証できる点も、この実験には不可欠でした。
実験と発見:AIが解き明かしたリーダーの3つの哲学
具体的な手順はシンプルです。
まず、note記事群 や会社の公式紹介記事 をNotebookLMにソースとして投入しました。
そして、「哲学の核心は?」「創業理念と現在の思想はどう繋がる?」といった問いを投げかけ、AIとの対話を重ねました。
その対話を通じて、私は、カンパニー社長の哲学を貫く3つの核心が、あると感じました。
1.現代の哲学者としてのエンジニア
AIが単純作業を代替する未来、エンジニアの真の価値は「どう作るか(How)」から「なぜ作るのか(Why)」へとシフトします 。それは、自らが作るものの倫理や社会的インパクトと真摯に向き合い、深く思考することです。技術だけが未来を築くのではない、という強いメッセージが込められています 。
2.究極のパフォーマンス指標としての「人間らしさ」
組織が過度に最適化され、合理性ばかりが追求されると、人は本音を隠し「演技する」ようになります 。しかし、真の強さと速さは、心理的安全性が確保され、弱さや「面倒くささ」を許容できる環境から生まれます。人間らしさを尊重することこそが、最高のパフォーマンスを引き出すという逆説的な真理です。
3.協働システムとしての組織
個人の力には限界があり、他者を頼ることは弱さではありません 。むしろ、人々が互いに協力し合うことで、一人では成し遂げられない目標を達成する。組織とは、そうした「協働システム」であるべきだという考えです。
応用編:AIを自己成長の戦略的パートナーにする
この洞察を、どう自分の目標設定に活かすか。ここからが、この実験のクライマックスです。AIを単なる分析ツールから、戦略的思考のパートナーへと変える試み。その鍵を握っていたのが、NotebookLMの「メモ」機能でした 。メモ機能は、NotebookLMが出力した内容を保存したり、マインドマップを出力しておいたり、自分の考えをまとめたドキュメントを保存しておくことができます。そのため、私は、自分の目標案をメモとして書き、それを新たな「ソース」としてAIに読み込ませました。そして、すべてのソース(カンパニー社長の哲学+私の目標)を選択し、こう問いかけたのです。
「あなたはカンパニー社長の哲学を理解したアドバイザーです。私の目標案をレビューし、会社のビジョンをより反映するための新しい視点を提案してください」
AIの回答は、単なる技術目標を「他者への貢献」や「チームの『余白』の創造」といった会社の核となる理念 に結びつけた、より高次元な目標へと再定義するものでした。
例えば、インフラエンジニアとAIエンジニアという私の役割を踏まえた「信頼性の高い開発基盤を整備し、その上で社内向けのAIツールを開発する」という目標を、「インフラエンジニアとして信頼性の高い基盤を提供することで他チームの認知的負荷を軽減し、さらにAIエンジニアとしてその上で開発プロセス自体を効率化するAIアシスタントを構築する。
これにより、組織全体の『余白』を創造し、より本質的な価値創造に貢献する」といった形に昇華させてくれたのです。
これは、AIが私の思考を拡張し、より戦略的な視点を与えてくれた瞬間でした。
結論:未来の働き方は「対話」である
カンパニー社長の思考をAIでまとめてみるという試みは、とても有効だったと感じています。
自分ではうまく理解できなかった部分を、AIに補ってもらうことで考えを深める一助になりました。
このツールを活用して目標設定に取り組むことで、カンパニー社長との面談でも、より深い対話ができるはずです。
お互いの本質を理解し合うことで、より良い仕事にもつながっていくと考えています。
そして何より、この取り組みを通じて、目標設定や評価面談も「ただの形式」ではなく、対話を通じた自己理解の機会へと変えていけると実感しています。
関連記事
- 【n8n × Slack】Gemini搭載のAIエージェント...
Tsai Yalin
- 技術選定の理由、即答できますか?AIとの対話で作る設計ドキュ...
Hideki Ikemoto
What is BEMA!?
Be Engineer, More Agile