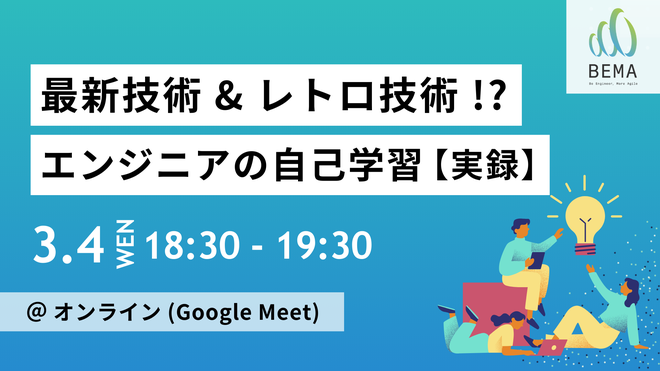「放課後の教室」みたいな場をつくるために。私が実践しているファシリテーションの11のポイント。
はじめに
初めてファシリテーションを任されたスクラムマスターやチームリーダーの方へ。
今から3年前、エンジニアからスクラムマスターにロールチェンジした当初、私は「ファシリテーター=司会進行役」くらいのイメージしか持っていませんでした。初めてのクライアント先で目標設定などのワークをファシリテートした際、ファシリテーションに関する知識やスキルが全くないまま臨んだため非常に苦労した記憶があります。
それ以来、本や動画などで学び、実践を重ねることで、自分なりのファシリテーションスタイルを築いてきました。この記事では、私がファシリテーションをする上で大切にしている心構えや具体的な方法をまとめたいと思います。
あくまで私個人の経験に基づいた「N=1」の知見ですが、誰かの役に立つことを願っています!
目指すは「放課後の教室での雑談」
私がファシリテーションの場で目指したいのは、「放課後の教室での雑談」のような雰囲気です。
これは「会社の定例会議」とは対照的な場だと考えています。
例えば、「会社の定例会議」のスタイルで放課後の遊びを決めるとどうなるでしょうか。
A「今日この後何する?一人ずつ案を出して多数決で決めようか。まずはB君からどう?」
B「ラーメン屋に行くのはどうかな?」
A「ありがとう。じゃあC君は?」
C「うちでゲームするのはどう?」
A「最後にD君は?」
D「公園でサッカーしようよ!」
A「じゃあ多数決で決めようか。賛成するものに手を上げてね。B君案がいい人?」
...
放課後の教室でこんな会話は行われるでしょうか?
おそらくですが、もっと自然な対話が生まれているはずです。
A「今日何する〜?」
B「それなら最近できたラーメン屋行ってみない?」
C「いいね!でも今そんなにお腹空いてないんだよな〜」
D「じゃあ先に軽くサッカーしてから行くか!」
A「賛成!うちにボールあるから持ってくるよ!」
このように「放課後の教室的な場」では、アジェンダに沿って話すのではなく参加者同士が対話を通じて新しいアイデアを創り出す「創発」が起こります。A案かB案かという二者択一ではなく、対話の中から全く新しいC案が生まれるのです。
会社内の会議はどうしても固い雰囲気になりがちですが、私は「放課後の教室的な場」をいかに作れるかを常に考えています。
私が実践しているファシリテーションのコツ|場を活性化する11個のポイント
心構え編
ファシリテーションをする上で、私が特に大切にしている心構えを3つご紹介します。
参加者を尊敬すること
かつての私は「ファシリテーションとは時間内に議論を収束させること」だと思っていました。議論の収束を阻むような振る舞いがあれば、無理やり自分が意図する方向へ誘導しようとしたこともあります。しかし、それでは良いアイデアは生まれません。参加者はそれぞれ独自の知識や経験を持ち、その状況下で真摯に行動している、という視点が欠けていました。
数々の失敗を経て、参加者一人一人の背景にある意図に目を向けることの重要性を学びました。沈黙している人を「やる気がない」と決めつけず、批判的な意見を「協調性がない」と判断しない。全ての行動の背景には肯定的な意図があると信じ、対話を促す姿勢を大事にしています。そして、その根底には「参加者を尊敬すること」という心構えがあります。
素直であること
ファシリテーションの前はいつも緊張するし、不安を感じます。しかし、その感情を隠して「完璧な自分」を演じようとして何度も失敗してきました。自分の弱さを開示することは勇気がいります。が、それを乗り越えて「今日は少し緊張しています」「準備のこの部分がまだ固まっていません」と伝えると意外とうまくいくんですよね。ファシリテーター自身が自己開示することで「この場は弱さを見せても大丈夫な場所なんだ」という心理的安全な場を作れるからなのかもしれません。
自分自身にも目を向けること
ファシリテーションをしていると「他者をどうするか?」という考えに支配されそうになるのですが、重要なのはまず「自分自身に目を向けること」だと思っています。
ファシリテーターは自分が思っている以上に場の雰囲気に影響を与えます。焦りやイライラはファシリテーターの振る舞いを通じて参加者に伝わり、最終的にはそれを反映した場になっていきます。だからこそ、自分の感情や状態を客観的に観察し、理解することが非常に重要だと感じています。
余談ですが、私は瞑想(マインドフルネス)がこの自己観察の姿勢を養うのに非常に有効だと思っています。瞑想は自分の呼吸を観察することで自身の中に生まれた考えや感情に気づき、手放すためのトレーニングです。筋トレのような感覚に近いかもしれません。私自身は継続的に瞑想トレーニングをすることで、ファシリ中でも「あ、今自分少しイライラしているな」とか「今ちょっと焦ってるな」と言うことに気づき、その状態を受け入れることで冷静にファシリテーションすることができていると感じています。
手段編
次に、私が実践している具体的なファシリテーションの手段をいくつかご紹介します。
場の目的を明示する
ミーティングの前に「その場が何のためにあるのか」を整理し、最初に参加者全員に伝えます。この目的が明確になり参加者の共感を得られれば、ファシリテーションの半分以上は完了したという感覚だったりします。放課後の教室での雑談ではAくんが「今日何する〜?」って言っただけで魅力的なアイデアが生まれましたよね。そんな場にしたいなといつも思ってます。
最初に雑談する
自分はミーティングの最初に雑談をすることが多いです。目的はアイスブレイクによって気持ちを切り替えたり発言をしやすい状態を作るためです。「それではアイスブレイクを始めます」のように形式的に行うのではなく、自然な形で雑談を挟み仕事のスイッチを切り替えることで「放課後の教室感」を演出できるように意識しています。
言葉使いを崩す
これも小さな心がけですが、できるだけ言葉使いを崩してコミュニケーションをとるようにしています。特にクライアント相手だと無意識に丁寧すぎるコミュニケーションになりがちですが、それが積もり積もって壁になってしまうこともあります。
「〇〇さん、ナイスです!」
「それめっちゃいいですね!」
「これ激ヤバですね」
「何が原因なんすかね〜これ。」
「とりあえずやってみましょ!!」
こういった言葉を使うことで心理的な距離を縮め、よりフランクな対話が生まれることがあります。この辺は自分の中にもギャルマインドが侵食しているのかもしれないです。
リアクションをする
「お通夜ミーティングどうしたらいいですか?」という相談を何度か受けたことがあるのですが、自分が原因の一部になっていることに気づけていないことが多い気がします。まずはファシリテーター自身がしっかりとリアクションをする。「なるほど」「うんうん」「あ、そういうことですね」といった簡単な相槌を打つだけでも場の雰囲気は大きく変わります。
発散→創発→収束の流れを意識する
ファシリテーションをするときは「まずはアイデアを発散させる」→「対話を活性化させてアイデアを創発する」→「最終的な結論に落とし込むように収束させる」という大きな流れを意識しています。めちゃくちゃ個人的なイメージなんですが、「ジャブを打ち続けて発散・創発し、最後に右ストレートを打って収束させる」ようなイメージを持っています。(ボクシングはやったことない)
ジャブ(発散・創発)
「今どんな課題がありますかね」
「この課題は何が原因なんですかね」
「最終的にはどんな状態になるといいですかね」
「その状態にするためにはどんなアイデアがありますかね」
「他にはどんなアイデアがありますかね」
「組み合わせられそうなアイデアはありますかね」
...
右ストレート(収束)
「来週のスプリントをより良いものにするためにどんなアクションが取れそうですか???」
ジャブを通じて必要な情報が洗い出せていれば、最後の右ストレートを打ったら自ずと結論がまとまっていくイメージを持っています。
問題対我々の構図にする
特に個人に紐づくような課題を話し合う場面では、「誰か対誰か」の対立構造が生まれがちです。このバーサス構造になると「どちらが正しいか」という議論が中心となり、創発的な対話が起きづらくなります。例えばこのような状況では、特定の個人から「振る舞い」を切り離し、できるだけ一般的な課題として提示することで、参加者全員でその課題を眺める「問題対我々」の構図を作ります。「どっちが正しいか」ではなく「どうすればより良くできるか」という議論が生まれて弁証法で言うところのアウフヘーベンが起きやすくなります。
miroなどのホワイトボードツールを使っているときは、みんなで眺めたい問題をデカデカを書いてみんなが見えるように置いておきます。そうすると物理的にも問題をみんなで眺める構図になり理想の構図を作りやすくなります。
ちなみにファシリテーターとしての自分が意見を言うのは基本的にこの構図ができた時だけにしています。そうしないとファシリテーター側の意見に引っ張られて創発的な対話が阻まれてしまう可能性があるためです。ファシリテーター自身も問題 対 我々の我々側に入り、フラットに情報を出すことでより良い結論にできるよう貢献することを意識しています。
議論の中身よりも議論の流れや参加者の状態を観察する
ファシリテーターが注視すべきは議論のコンテンツ(中身)ではなく議論の流れ(プロセス)だと思っています。議論の流れや参加者の様子などを客観的に観察し「これはこういうことかな?」と解釈する。そして、もし介入が必要だと判断すれば問いかけを投げたりすることで場に介入するようにしています。
こういうことが自分不在でも自然と行われる仕組みを作る
私が最終的に目指しているのは、こういったファシリテーションが自分不在でもチーム内で自然と行われるようになることです。例えば、チーム内でファシリテーションができるメンバーを育成する、みんなでファシリテーションについての勉強会をしてみる、などを実践していますがまだ道半ばです。これは非常に難しいと思っていますが不可能ではないと思っています。放課後の教室で僕らは自然とやってたはずなので。
さいごに
この記事では、ファシリテーターとしての私の経験から、「放課後の教室での雑談」のような創発的な場を作るための考えをまとめてみました。
繰り返しになりますが、あくまでN=1の知見でしかないので、これが正解だとは思わないでほしいです。そして、もしご意見やご感想あればいただきたいです!
この記事が、ファシリテーションに取り組む皆さんの一助となれば幸いです。
この記事を書いた人

What is BEMA!?
Be Engineer, More Agile