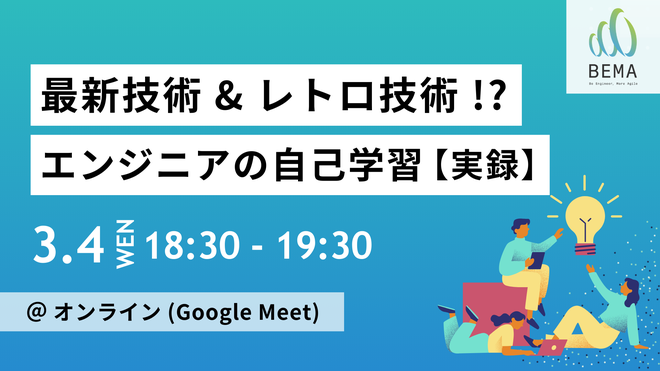海外インターンシップ受け入れ体験談!インドの学生と挑んだスクラムと文化の学び
はじめに
私はこれまで日本人メンバーのみのチームに関わってきたのですが、今回インドからの学生インターンシップを受け入れる弊社の施策に関わる機会をいただきました。
そこで本記事では、これまでとは全く勝手が違う中で、挑戦した取り組みや、その中で感じた学びをお伝えします。
特にグローバル人材の受け入れを検討しているチームのマネージャーや受け入れが決まったチームのスクラムマスターの方にとって、少しでも参考になれば幸いです。
インターンシップ受け入れの概要
こちらの記事でも紹介されていますが、弊社のメンバーが2025年2月にインドへ訪問し学生との交流や現役のエンジニアとの交流を通じた現地理解を行いました。
その後、色々とありインドからの学生をインターンシップとして受け入れることになりました。
具体的には以下になります:
勤務形態
フルリモート(インド現地からの就業)
受け入れ人数
5名
インターンシップでの業務内容
フルスタックエンジニアとしての開発業務
受け入れ期間
5月12日から7月21日まで(50営業日)
今回のインターンシップでは、個別に業務に関わっていただくものではなくインターンシップ生全員で1つのチームとして社内で利用を目的とした、「チームの開発生産性可視化のためのプロダクト開発」に関わっていただきました。
チームのスプリントサイクルとコミュニケーション
今回のインターンシップでは、1週間を1スプリントとするスクラムでの開発を行いました。
月曜日:スプリントプランニング
火曜日:リファインメント
水曜、木曜日:スプリントイベントは行わず、開発日!
金曜日:スプリントレビュー&レトロスペクティブ
実際にインターン生と共有するために作ったカレンダー
インドのメンバーが現地からの参加のため、現地の始業時間に合わせ、業務開始の確認もかねた形式のDaily Sync upを毎朝行いました。
日本、インドそれぞれ現地から参加のため、どうしても時差が発生します。
それによって、業務開始時のコンディション確認と、終了時の確認が難しいという課題がありました。そこで、Slackのワークフローで業務開始のコンディション共有と、簡易日報アプリを作り、業務開始時と業務終了時に提出してもらいました。
それぞれ、以下内容を回答してもらい、日本が先に業務開始したタイミングで確認し必要なフィードバックをしていきました。
コンディション確認(業務開始時)
今日のコンディションを教えてください!
1~5段階評価でレーティングしてもらう
前日の作業で発生した障害など、相談しておきたいことはありますか?
作業を開始するにあたって確認、質問したいことはありますか?
日報(業務終了時)
業務を終えてのコンディションを教えてください!
今日はどんな業務を行いましたか?
今日の作業の中で相談や質問したいことはありますか?
この日報の回答はSlackのスレッド内にオープンにして、お互いが困ったところを相談するキッカケにしてもらったり、我々のフィードバックやインターンシップの評価を行う材料としても活用することができました。
日常のコミュニケーションはSlackを通じたテキストメッセージを中心に、google meetを利用したオンライン通話も活用していきました。
ただ、スクラムマスターとインターンシップの事務局という立場を兼務する中で、密なコミュニケーションを取るにはミーティングだけでは足りないと感じる機会も多く、1on1を週に一度行うことにしました。
初めての海外インターンシップ受け入れを通じて得られた学び
今回、初めての海外インターンシップ受け入れを行ったことで、多くのことを感じました。
これまで、日本国内の学生インターンシップや、面接対応で感じてきたことと比較しながら、学びを幾つか挙げます。
※どちらが採用に有利かといった優劣の話ではありません。
文化的な要素の違い
今回のインターンシップの中で特に感じたのが文化面の違いです。
コミュニケーションを密にとっていく中で、宗教観や地域性、それらによってもたらされる価値観の理解をすることがやはり難しかったと感じました。
今回参加メンバーはインド国内でもいくつかの地域に離れて暮らすメンバーでした。
そのため、メンバーそれぞれの地域の地理的な特徴やそこからくる気候の違い、電力などの事情毎にインターンシップ中いろいろなトラブルが発生しました。
都度、起きたことにできる範囲で対処していったつもりではありますが、彼らがどう受け取ったのかは測りきれない部分を感じました。
出来事への対処やコミュニケーションをしていく中で、「どんなことを彼らは大切にしているのか」「彼らの環境でどんなことが実現可能なのか」を理解しながら対処するのはそれぞれが現地での業務ならではの難しさを感じました。
インド視察に行ったメンバーへのヒアリングや、文化の学習を通じて理解をしようと取り組んできた結果、インターン生が考えることの背景の輪郭を捉えることができた感覚です。
そのうちの一つとして、インドの学生インターンシップは、日本のように複数企業に幾つか参加するものではなく、1つの企業に参加して長期的に参加して就職活動に向けてそのまま進んでいくことが主になっています。
そのような背景から、1on1などの機会で自分自身のスキルのアピールももちろんありましたが、それ以上にたくさんのフィードバックを求められます。長期間のインターンシップに参加することで、自分自身をその企業に合わせて変えていこうという姿勢が特に印象に残りました。
合わせて、インドの文化面の理解を深めるために、行動や会話を通じて体感することを特に意識していました。
例えば、直接インターン生にデイリースクラムの後に雑談として普段の生活の様子などを聞いたり、逆にインターン生が興味を持つ日本の文化などについての会話を積み重ねる時間を重視していました。受け入れ期間中に出張やプライベートでの遠出があったため、出かけた地域に関する話は特に色々と興味を持って質問をもらいました。
また、体感しやすいインド文化として食事に関して色々と質問をした上で、インド料理のお店に食べに行ったりと、共通の体験を作ることを大事にしました。
共通の体験があることで、全てとは言えませんが理解の一助にはなったと感じています。
写真はインターン生から教えてもらって万博で食べてみたパニ・プリという料理
パーソナリティの傾向としては、今回参加したメンバーの傾向として奥ゆかしさがある傾向を感じました。そういった部分は日本人にも通じる部分があると感じながら接していました。ただ、それだけではなく、気になったことや挑戦したいことは積極的にアピールするなど使い分けが上手な印象を持ちました。
(あと、日本のアニメ・漫画の人気さを実感させられました。漫画・アニメがあまり得意でなく、話題が出せなかったのは申し訳なさまで感じました、、、)
技術に対する素直さ
エンジニアを目指すインターン生さんの技術に対する興味やそれにまっすぐ向き合う姿勢を感じました。
また、「興味があって学んできた」だけでなく、「学んだ結果からさらにこの領域を深めたい」や「こんな領域にも興味があり関わっていきたいんだ」という想いの強さを感じました。
週次で学生さんとの1on1を通じたコミュニケーションを継続的に行ってきたのですが、その中でも「こんな技術をこれまでやってきて、今回のプロダクトでもこんなことをしたい」や「こんな技術に対して興味がある。この開発でこんなことはできないか?」などの話が多くありました。今回のチームへの関わり方の中でどんなコミュニケーションを通じてそれを実現できるかや、そのためにどのようなアイデアを持っているか具体も含めて話してもらえるための工夫が今後さらにできると良いかと思いました。これまでのコーチングやファシリテーションだけでなく、英語で含まれるニュアンスや文化によって違う発言の仕方なども考慮が必要で難易度の高さを感じました。
コミュニケーションの難しさ
今回、海外インターンシップ受け入れを担当しましたが、私は元々特に英語が話せるわけではありません。読む分には不都合ないけど書いたり話したりはできない状態でした。だからといって、インターン生の皆さんが日本語が堪能な方ではないという難しい状況でした。
英語圏にルーツがある弊社メンバーに通訳として入ってもらいましたが、一日中つきっきりになることはできず、スクラムイベントなど優先するタイミングのみの最小限の範囲でした。
また、議論の中で話した内容をどのように受け取ったかをお互いに認識を合わせるという観点での議事録の役割の大きさを実感しました。ステークホルダーからのフィードバックなどをどのように受け取ったのか、チームのメンバーに言語化して書き出してもらうことで我々からも確認や訂正ができる状態になるのはとても安心感がありました。
そんな中で、ビデオ会議に使ったGoogle Meetの音声通訳機能に助けられた部分はとても大きかったと思います。精度がかなり高いわけではなかったですが、トンチンカンで何もわからないような事態にはならず補助としては優秀でした。
また、翻訳がそういった精度であることをお互い認識できたことでチャットツールを使ったコミュニケーションを補助として活用するなどお互いに工夫を積み重ねることができたのは運営、インターン生という立場を超えたチームとしての良い状態だったと感じています。
そんな経験を土台に、自分とインターン生の「英語話せない」と「日本語話せない」な1on1を実践することができました。
お互いに翻訳の特性を理解した上でコミュニケーションを取ることで、相互理解を深めることができたのは大きな成果だったと思います。
インターンシップ終了時の全メンバー集合写真!やりきった表情をいただきました!
最後に
今回のインターンシップを通しての学びについて、10月4日(土)のスクラム祭りにてスピーカーをさせていただきます!
この記事では取り組みとそこから見えた事実や知見が中心となりました。
スクラム祭りでのセッションは、この取り組みを通じたスクラムマスターとしての学びや成長できたところなどもう一歩深い話をできればと考えていますのでそちらも是非お楽しみに!
(2025/10/21更新)
上記で紹介した発表資料を公開しました!
こちらの記事で書いた内容以外の学びを記載していますので興味を持っていただいた方は是非こちらもご覧ください!
この記事を書いた人

What is BEMA!?
Be Engineer, More Agile