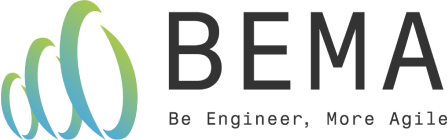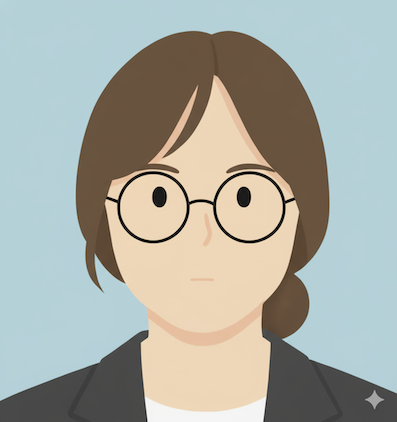DifyとLangfuseを使ったプロンプト改善の仕組みの検討
こんにちは、株式会社メンバーズデブオプスリードカンパニーの兼子です。
インフラエンジニアとして10年、私はシステムの「測定」と「改善」を繰り返してきました。CPU使用率、レスポンスタイム、エラーレート。これらの数値を見ながら、ボトルネックを特定し、改善し、また測定する。この当たり前のサイクルが、LLMアプリ開発では意外と回っていないことに気づきました。
「このプロンプト、なんとなく良さそう」「前より悪くなった気がする」
そんな曖昧な判断で、本当に良いのだろうか。DevOpsで培ってきた「測定可能性」の考え方を、LLMアプリ開発にも適用できないだろうか。
そう考えて導入したのが、DifyとLangfuseの組み合わせでした。
本記事の核:1分でわかる連携の価値
この記事で得られる3つのこと
Difyで高速開発 → ノーコードで数時間でLLMアプリを構築
Langfuseで測定可能な改善 → プロンプトの効果を数値で評価し、PDCAを高速に回す
DevOpsの知見をLLMアプリへ → 「Observability」「測定→改善」のサイクルをプロンプト開発に適用した実感
一言で言えば: Difyで作り、Langfuseで測定し、改善サイクルを回す。DevOpsでやってきたことを、LLMアプリ開発でも実現する仕組みです。[1][2]
Dify × Langfuse:役割分担で回す改善ループ
この2つのツールは、開発と改善で明確に役割が分かれています。
フェーズ | 担当ツール | 主な機能 | 実務での価値 |
|---|---|---|---|
1.つくる(開発) | Dify | • ビジュアルワークフロー • RAG機能(PDF/CSV取り込み) • マルチLLM対応 • API連携 | 非エンジニアでも数時間でプロトタイプ構築。 複雑なAIロジックをドラッグ&ドロップで実装。 |
2.みる(観測) | Langfuse | • トレース機能(実行ログ可視化) • コスト・パフォーマンス分析 • トークン数・レイテンシ計測 | ブラックボックスを解消。 「どこが遅いか」「なぜコストが高いか」を即座に特定。 |
3.直す(改善) | Langfuse × Dify | • 実行ログの分析 • A/Bテスト • 評価機能(人間/LLM自動評価) • バージョン比較 | 改善の効果を数値で測定。 「なんとなく」ではなく、データで判断できる。 |
この表が示す核心: 開発はDifyで完結させ、改善ループはLangfuseで高速に回す。インフラの世界で当たり前だった「測定→改善」のサイクルが、LLMアプリ開発でも回せるようになりました。
3ステップの改善サイクル
DevOpsで慣れ親しんだサイクルを、プロンプト改善にも適用できました。
1. つくる(Dify)
何をするか: 数時間でプロトタイプを構築
ドラッグ&ドロップでワークフローを組み立て
RAG機能で社内ドキュメントを取り込み
複数のLLM(GPT-4、Claude、Geminiなど)を使い分け
成果物: 動くAIアプリケーション
2. みる(Langfuse)
何をするか: 実行ログを可視化し、ボトルネックを特定
API Keyを設定するだけで、Difyの全実行がLangfuseに自動記録
トレース画面で「どのステップに時間がかかっているか」「コストはいくらか」を確認
エラー発生箇所を即座に特定
成果物: 改善すべきポイントのリスト(レイテンシ、コスト、品質)
3. 直す(Dify × Langfuse)
何をするか: 測定結果をもとに、改善のプロセスを回す
Dify上でプロンプトを修正(プロンプトはDify内に置いたままでOK)
Langfuseで実行ログを確認し、改善の効果を数値で測定
複数バージョンをA/Bテストで比較し、最適なものを選択
うまくいかなければ、ログを見て原因を特定し、再度修正
成果物: 継続的に品質が向上するAIアプリケーション
重要なのは、この3ステップを回し続けられる「視点」を持てたことです。インフラの世界では当たり前だった「メトリクスを見て、仮説を立て、改善し、また測定する」というサイクル。それがLLMアプリ開発でも実現できると分かったのが、最大の収穫でした。[3]
実際に運用してみて、やってよかったこと
ここからが、この記事で最もお伝えしたい部分です。DevOpsエンジニアとして、Langfuseを導入して実感した3つの「よかったこと」をご紹介します。
1. 個人の感覚ではなく、「測定可能な指標」で改善できるようになった
従来、プロンプトの良し悪しは個人の感覚や経験に依存していました。
「このプロンプト、なんとなく良さそう」
「前より悪くなった気がする」
インフラエンジニアとして、こういう曖昧な判断には常に違和感がありました。CPUが「なんとなく重い気がする」では改善できない。数値で測定し、ボトルネックを特定し、改善する。それがDevOpsの基本です。
Langfuseを導入したことで、レスポンス時間、トークン数、コストといった具体的な数値が可視化されるようになりました。
何が変わったか:
「速くなった気がする」→「P95レイテンシが200ms改善」
「コストが心配」→「1実行あたり0.03ドルから0.02ドルに削減」
「品質が上がった」→「評価スコアが平均3.2から4.1に向上」
数値で語れるようになったことで、改善の効果を定量的に示せるようになりました。これはまさに、DevOpsにおける「測定可能性(Measurability)」の考え方そのものです。
プロンプト改善の優先度判断も、感覚ではなくデータで行えるようになりました。
2. チーム全員が「同じ視座」でプロンプトを見られるようになった
以前は、プロンプトの改善がエンジニア個人のスキルに依存していました。
「Aさんはプロンプトが上手い」
「Bさんはまだ慣れていない」
この「属人化」も、インフラの世界では避けるべき状態です。誰か一人しか触れない環境、誰か一人しか理解していない設定。そういう状態は、チームの脆弱性になります。
Langfuseで実行ログとメトリクスを可視化したことで、誰でも同じ情報を見て、同じ基準で判断できるようになりました。
何が変わったか:
プロンプトの変更履歴が全て記録され、「誰が、いつ、なぜ変更したか」が明確
過去のバージョンと現在のバージョンを並べて比較可能
エンジニア以外のメンバー(企画、ビジネス側)も実行ログを見て議論できる
これにより、複数人で同じ目線でプロンプトを改善できるようになりました。DevOpsの「透明性(Transparency)」と「共通言語」が、LLMアプリ開発にも適用できた実感があります。
個人のスキルに頼るのではなく、チーム全体で改善サイクルを回せる。これは、持続可能な開発体制を作る上で非常に重要だと感じています。
3. DevOpsのように「測定→改善」のPDCAサイクルを回せるようになった
インフラエンジニアとして、これが最も感動したポイントです。
DevOpsでは「メトリクスを測定し、ボトルネックを特定し、改善する」というサイクルを回します。Prometheus、Grafana、Datadog。ツールは違えど、本質は同じです。
「測れないものは、改善できない」
この原則が、LLMアプリ開発でも実現できました。
具体的なサイクル:
Plan(計画) → Langfuseで現状のメトリクスを確認し、改善ポイントを特定
Do(実行) → Difyでプロンプトを修正
Check(評価) → Langfuseで効果を測定。評価スコアとメトリクスで比較
Act(改善) → 効果の高いバージョンを本番適用。効果が薄ければ再度改善
このサイクルを数時間〜数日単位で高速に回せるようになったことで、プロンプトの品質が継続的に向上していく実感があります。
改善のプロセスを回せる「視点」を持てたこと
これが最大の収穫でした。ツールの使い方を覚えたのではなく、「LLMアプリ開発でも、測定→改善のサイクルを回せる」という視点を得られたのです。
インフラの世界で「Observability(可観測性)」「Infrastructure as Code」が当たり前になったように、LLMアプリ開発でも「測定可能な改善サイクル」が重要になると感じています。
Dify × Langfuseは、DevOpsエンジニアが持つ知見を、LLMアプリ開発に活かせることを教えてくれたツールセットでした。
まとめ
Dify × Langfuseの組み合わせは、LLMアプリ開発に「測定→改善」のサイクルをもたらします。
この記事の核心:
Dify → 高速な開発基盤(数時間でプロトタイプ)
Langfuse → 測定可能性の提供(メトリクスと実行ログの可視化)
改善サイクル → DevOpsで培った知見を、LLMアプリ開発に適用
DevOpsエンジニアとしての実感:
インフラの世界で当たり前だった「測定→改善」のサイクルが、LLMアプリ開発でも回せることが分かりました。ツールは違えど、本質は同じ。「測れないものは、改善できない」という原則は、どの領域でも変わりません。
Dify × Langfuseは、DevOpsエンジニアが持つ知見を、新しい領域に活かせることを教えてくれました。
関連記事
- 【n8n × Slack】Gemini搭載のAIエージェント...
Tsai Yalin
- 技術選定の理由、即答できますか?AIとの対話で作る設計ドキュ...
Hideki Ikemoto
What is BEMA!?
Be Engineer, More Agile