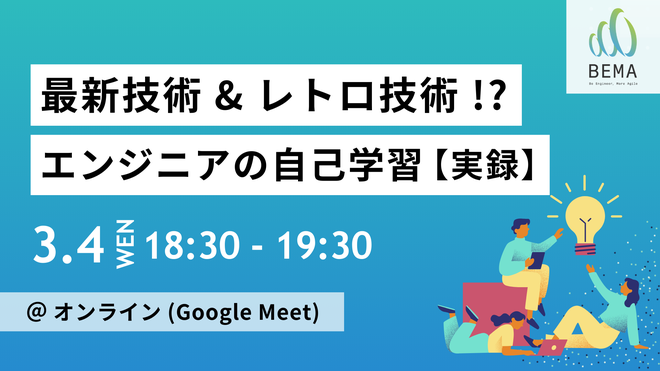【第4回/サーバーの核心に迫る!物理サーバーと基礎知識】日本CTO協会主催 新卒エンジニア合同研修潜入レポート
はじめに
本レポートは、第4回CTO研修の主要な学びと洞察をまとめたものです。
この研修では、サーバー解体とサーバーの基礎知識に焦点を当て、ourly株式会社、GMOペパボ株式会社からの実践的な知見、そしてDELL Technologiesの福田昭良氏によるサーバー基礎講座を通じて、参加者の理解を深めることができました。
※会場は、GMOインターネットグループ様よりご提供いただいた「GMO Yours(渋谷フクラス)」にて開催されました。
この記事では、物理サーバーの歴史、その利点と課題、そしてサーバーを構成する各主要パーツの役割について解説し、ITインフラの根幹をなすサーバー技術の重要性を再認識することを目的としています。
GMOインターネットグループ様ご提供「GMO Yours(渋谷フクラス)」
研修のオープニング:意思決定の重要性
研修の冒頭では、ourly株式会社の相澤宏亮氏より「意思を持とう」というメッセージが伝えられました。意思決定の回数が多いほど成長速度が上がると強調されており、意思とは単に思ったことだけでなく、最後まで責任を持てるかどうかが重要であると説明されました。
上司の意見で進めるのではなく、自ら「なぜこれをしたいのか」を考え、決断することが個人の成長につながるとの示唆をいただきました。
GMOペパボのサーバー利用史:物理サーバーの魅力と挑戦
GMOペパボ株式会社は、サーバーレンタルサービス「ロリポップ!レンタルサーバー」が最初期にPCサーバーで稼働を開始するなど、物理サーバーから歴史をスタートさせています。
現在は複数のデータセンターを乗り継ぎながら3000台以上のサーバーを運用しており、一時期は自作サーバーへの挑戦も行われたそうです。同社はパブリッククラウドとの併用を進めていますが、物理サーバーとクラウドサービスは対立するものではなく、共存する関係にあると強調されていました。
物理サーバーのメリット
自由度の高い構成: 自分たちのやりたいことに沿った構成をしやすい点が挙げられます。目的や用途によっては、パブリッククラウドよりもコストを抑えることが可能です。
メガクラウドへの非依存: 特定のメガクラウドサービスに依存しない運用が可能です。
デジタルガジェット的な魅力: 物理ハードウェアを扱うこと自体に楽しさがあり、コスト削減にも貢献できると感じられます。
大規模利用の可能性: 例えば、写真共有サービスで18台のストレージサーバー、376本のHDD、約5.8ペタバイトの容量を持つ超巨大サーバーを利用する事例も紹介されています。
物理サーバー運用の課題
物品管理の煩雑さ: 台数や機種が増えると、物品の管理が非常に面倒になり、管理コストが増大してしまいます。
スペックに対する責任感: ハードウェアは高額であるため、導入製品のスペックに対する責任感が大きく、要件定義、検証、ベンチマークを厳密に行う必要があるそうです。
老朽化対策: 長期間使用すると故障率が上がるため、適切なタイミングでサービスから除外・退役させ、新製品と入れ替える必要があります。
外部要因の影響: 2011年のタイ大洪水のように、特定の時期に製造されたハードディスクの故障率が上がるなどの外部要因による影響を受けることもあるそうです。
GMOペパボは、最初からクラウドを利用するのも良いが、オンプレミスという選択肢を持てるとさらに良い、と締めくくられていました。
サーバー基礎講座:DELL Technologies 福田昭良氏による解説
DELL Technologiesの福田昭良氏からは、サーバーの基礎に関する詳細な解説をいただきました。
サーバーとは何か?
サーバーとは、ネットワーク上で他のコンピューターからの要求を処理し、サービスを提供するハードウェアのことです。要求を送信する側はクライアントと呼ばれており、この仕組みがクライアントサーバー方式です。
一般的なコンピューターとの大きな違い
サーバーは一般的なコンピューターとはいくつかの点で大きく異なります。
稼働時間: 365日24時間動き続けることが前提となっています。
利用者: 複数の利用者が同時にアクセスします。
影響度: 故障した際の影響が非常に大きいため、継続性と冗長性が極めて重要視されます。
コスト: 一般的なPCと比較して高価です。
サーバーの構造と筐体タイプ
サーバーの見た目の種類には、タワー型(据え置き型)、ラック型(ラックマウント型)、ラックスケール型があります。
主要構成パーツの詳細
CPU (中央演算処理装置): サーバーの「脳」にあたる部分で、IntelとAMDが主要なメーカーです。搭載数(ソケット数)、クロック数(GHz)、コア数、スレッド数が性能の指標となります。特にコア数が増えることで同時処理能力が向上しているそうです。
メモリ (RAM): アプリケーションや演算に利用される「作業スペース」です。容量(GB)が大きいほど同時処理能力が高まります。メモリにもクロック数(GHz)があり、サーバーへの搭載にはルールに従って、Intelでは8の倍数、AMDでは12の倍数で搭載することが推奨されています。サーバーメモリにはECC(Error Checking and Correcting)機能が備わっています。メモリ上で発生したシングルビットエラーを検出・訂正することで、太陽からの宇宙線などによるデータの破損を防ぐことができる機能です。複数のメモリモジュールを並行して持つことで、スループットを高める設計もあるそうです。PC用のメモリをサーバーに使うと故障する可能性があるため注意が必要です。
HDD/SSD (ストレージ): メモリへ展開されていないデータの保管場所です。
HDD (Hard Disk Drive): 磁気で記録されており、書き込みが比較的遅い特徴があります。
SSD (Solid State Drive): パフォーマンスが非常に高く、故障率が低いですが、容量あたりの単価が高いという特徴があります。
接続方式: データの読み書きのボトルネック解消のため、接続方式が重要です。SAS/SATA方式(主にHDDで利用)はデータが一本道になりIO渋滞が起こりやすいですが、NVMe方式(主にSSDで利用)はパラレルでIOが可能であるためボトルネックが起こりにくく、故障率も低いとされています。
RAIDコントローラー: 複数のディスクを束ねて仮想化し、データ永続化や耐障害性を高める装置です。PCIスロット搭載式やバックプレーン装着式があります。
FAN (冷却ファン): サーバー内部の冷却に使用されます。効率的な冷却のため、ファンの向きとメモリの向きが同じになるように設計されていることもあるそうです。
PCI Slot (PCIスロット): 拡張カードを接続するためのスロットです。
電源モジュール: サーバーに電力を供給します。
ネットワークIF (NIC): サーバーを別のサーバーやクライアントへ接続するための接続口です。通信速度(Gbps)は高速で、800Gbpsに対応するサーバーもあるそうです。サーバーとクライアントを直接繋ぐことは少なく、通常はネットワークスイッチを介して接続されます。
サーバーならではの付加機能
iDRAC (integrated Dell Remote Access Controller): Dell PowerEdgeサーバーのリモート管理ツールであり、IPMIに準拠しています。iDRACにIPアドレスを付与することで、ネットワーク越しにサーバーを管理でき、仮想コンソール機能や故障箇所の特定などが可能です。
パーツの冗長化: サーバーの停止を防ぐため、電源やディスクなど各パーツにおいて冗長性が確保されています。これにより、パーツ単位での障害が発生してもシステムに影響を与えることなく交換できる設計になっています。
サーバー解体研修感想
サーバー解体研修では、グループに分かれてサーバーの解体を体験しました。サーバーはパソコンと比較して大きく、重量もありました。特筆すべきは、ドライバーなどの工具を使わずに、ある程度まで解体できる設計になっている点です。そのため解体するのは容易でしたがそれを元に戻すのは大変でした。
他の企業から参加されたエンジニアの方々と密にコミュニケーションを取りながら、どこに問題があるのかを検討し、試行錯誤を重ねた結果、無事にサーバーを元の状態に戻すことができました。この経験を通じて、チームで協力し、課題を解決していくことの重要性を改めて認識しました。
今回のサーバー解体研修は、サーバーに関する知識を深めるだけでなく、解体作業の面白さをエンジニア間で共有できる貴重な機会となりました。また、他社のエンジニアとの交流の場としても大変有意義であり、今後の業務に活かせる多くの学びがありました。
サーバー解体中の画像
開封されたサーバー
おわりに
今回の日本CTO協会主催の新卒合同研修を通じて、物理サーバーが依然として重要な選択肢であり、クラウドと対立するものではなく共存しうる存在であることが再確認できました。また、サーバーの各構成パーツが果たす役割と、それらが一体となって安定したサービス提供を支えていることを深く理解することができました。
また、サーバー解体研修ではエンジニアの横のつながりを強く感じることもできました。
今回の研修で得たサーバーの基礎知識とエンジニアのつながりを活かして、エンジニアとして成長していきたいと思います。
最後まで読んでいただきありがとうございました!
次回の取材レポートもぜひご覧ください!
関連記事
- BEMA賞 受賞者に聞く、“楽しく”続けてチャンスを掴むアウ...
BEMALab 編集部
- 【2025年12月版】人気記事ランキング|スクラム・キャリア...
BEMALab 編集部
What is BEMA!?
Be Engineer, More Agile