コミュニティ運営は“楽しんだもん勝ち”!スクラムフェス仙台の4年間から学ぶ、続けられる場づくりの知恵
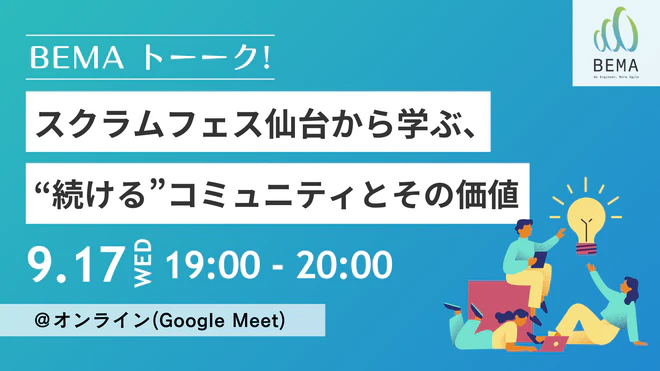
こんにちは、BEMA Lab編集部の濱松です!
2025年9月17日、スクラムをテーマにしたコミュニティ「すくすくスクラム」と、BEMAで共催イベントを開催しました。テーマは「スクラムフェス仙台から学ぶ、続けるコミュニティとその価値」。
インタビュアーは現実行委員長のメンバーズ・小島啓輔さん、ゲストは元サイボウズで前実行委員長を務めた天野祐介さん。仙台オフィスに10名ほど、オンラインに10名ほど集まり、少人数ながらその分距離が近くて、とても温かい雰囲気でした。
今回はその中から、編集部が「なるほど!」と心に残ったトピックをお届けします!
「スクラムを知らなくても楽しい!」スクラムフェス仙台が愛される理由
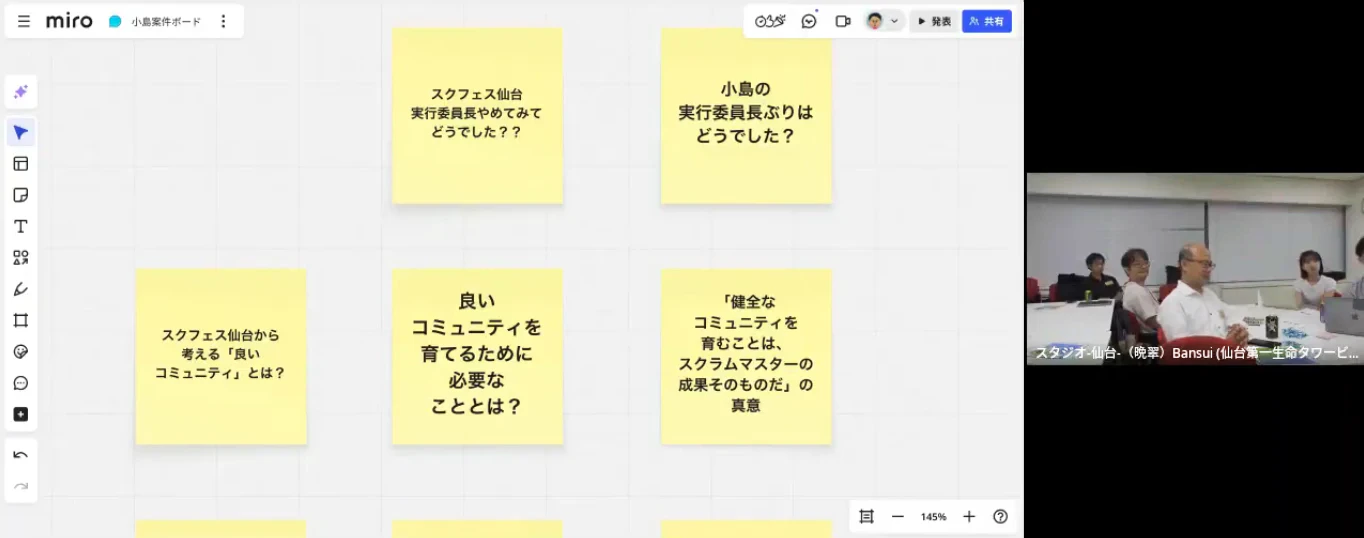
紹介された参加者の声が、どれもリアルでグッときました。
- 「スクラムは詳しくなかったけど、知らない人と交流できて楽しかった」
- 「エンジニア同士でキャリア相談ができた」
- 「興味あるテーマを話したら、その分野に詳しい人をすぐ紹介してくれた」
チャットでも「スクラムを知らなくても楽しめるのがすごい!」といった声もあって、専門知識の有無にかかわらず誰もが楽しめるオープンな雰囲気。これが、スクラムフェス仙台の大きな魅力であることが分かりました。
実は私もこの日、スクラムフェスにオンラインで初参加!

SNS発信を担当したのですが、スクラムフェスのメインツールはDiscord。これが初めてだったので「オンラインでちゃんと雰囲気を味わえるのかな…?」と少し不安だったんです。
でもその心配はすぐに吹き飛びました!
終盤には「現地の熱気すごすぎ!次は絶対行きたい!」と本気で思ってしまうほど。
スクラムやアジャイルの知識があるかどうかは関係なく、「楽しみたい!」という前向きな気持ちさえあれば誰でも自然に溶け込める場なんだ、と肌で感じました。
私のスクラムフェス仙台の参加レポートは、以下の記事からご覧いただけます!
4年間続くコミュニティの秘訣は「運営がまず楽しむこと!」
ボランティア運営のコミュニティが、どうして4年も続いているのか?
その答えはとてもシンプルでした。
天野さんと小島さんが口を揃えて言ったのは「運営が楽しんでいること」。
運営が本気で楽しんでいると、その熱が自然と外に伝わり、気になった人が新しく参加してくれる。そうやって「楽しさの循環」が回っていくのだそうです。
もちろん、参加者の期待に応えようと頑張りすぎると運営側が疲れてしまうこともあります。だからこそ「まずは自分たちが楽しむこと」が大事。そこに共感してくれる人が自然と集まってくる。この考え方に、会場でも多くの人が大きくうなずいていました。
コミュニティ運営スキルは「キャリアの加速装置」

さらに印象的だったのが「コミュニティ運営スキルはキャリアに直結する」という話。
コミュニティ運営は、コーチングやモチベーション管理、エンゲージメントを高める工夫を自然と身につけられる。
「人のパフォーマンスを引き出す経験」は、チームを率いる立場になったときにも大きな武器になる、と天野さんは話していました。
この視点は私にとっても、目から鱗!正直、私はコミュニティ活動って「プライベートの延長」くらいに思っていたのですが……実はキャリアの加速装置だったんです。人を巻き込み、一緒にゴールへ向かう力は、これからどんな職場でもリーダーに欠かせないスキルだと改めて実感しました。
人数よりも「関係性の深化」―理想のコミュニティって?
では、理想のコミュニティってどんな姿なんでしょう?
天野さんと小島さんが強調していたのは「人数の多さ」ではなく「関係性の深まり」でした。
固定メンバーだけでなく、新しい人が気軽に参加できる「開かれた場」であること。そのためにオンライン配信や録画を残すといった工夫も紹介されていて、「なるほど、窓口を広げるってこういうことか!」と編集部もハッとしました。
そして健全なコミュニティには「リスペクトと協力」が欠かせない。
自分だけ得をしようとする「テイカー」ではなく、互いに支え合う人が集まってこそ、いい場が育つんだよね、という言葉も印象的でした。
私たちBEMAも「より良いエンジニアであり続けよう」を合言葉に、エンジニア同士の交流を大事にしています。今回の「まず運営が楽しむ」という考え方は、まさにBEMAが大切にしてきたことと重なっていて、とても共感しました。
「段階的な関わり」がコミュニティを強くする
天野さんが話してくれた「コミュニティへの関わり方のステップ」も、とても分かりやすかったです。
- 外から見る:SNSのハッシュタグで雰囲気をのぞいてみる
- 参加してみる:気になるイベントにまず足を運んでみる
- 近づく:運営をちょっと手伝ってみる
こうやって少しずつ中心に近づいていけるから、誰でも自分のペースで関われる。
「段階的に関われる仕組み」があるからこそ、新しい人が入りやすく、代謝が回り続けるんだなと感じました。
オンライン配信やイベントレポートも、まさにその入り口のひとつ。今回の記事も「まずは外からのぞいてみる」きっかけになれば嬉しいです!
編集部まとめ:楽しさから始まる、持続可能なコミュニティづくり
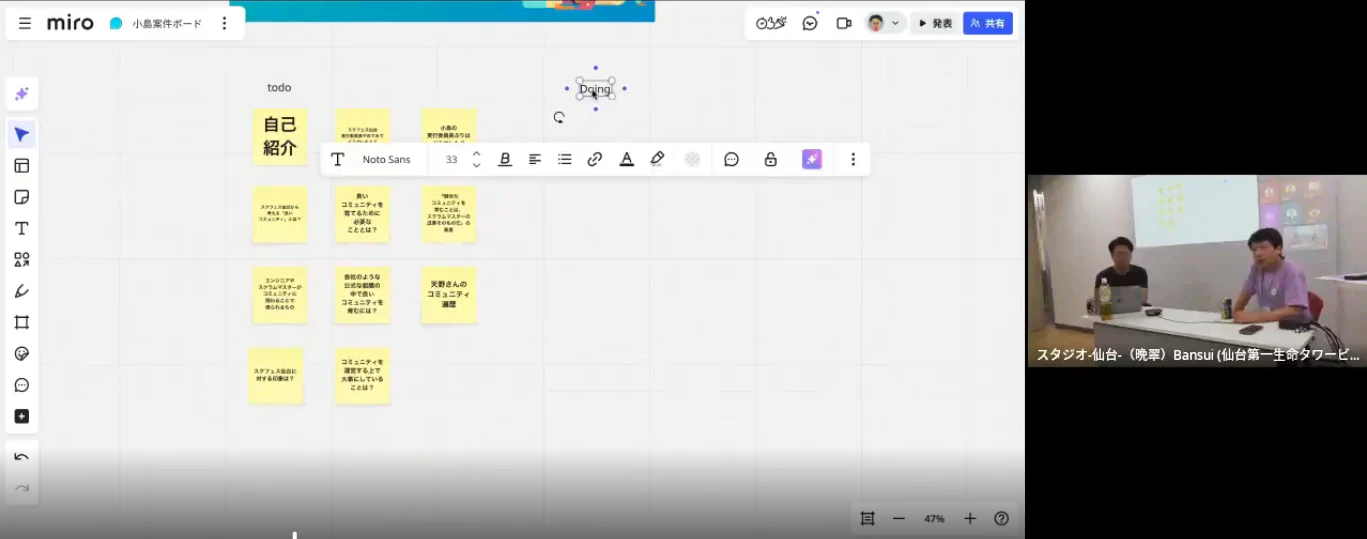
今回のイベントを通して一番響いたのは「コミュニティ運営の原動力は“楽しさ”だ」ということ。
運営者が楽しみ、そのワクワクが周りに伝わって広がっていく――それがコミュニティを自然に成長させる力なんだと強く感じました。
このシンプルだけど本質的な考え方は、「これからコミュニティを立ち上げたい」「運営を続けるのが大変…」と悩んでいる人にとって、大きな勇気になるのではないでしょうか?
印象的だったのは、「社外コミュニティをまず実験の場にする」という視点です。社内でいきなり大きな変革を起こすのは難しいけれど、コミュニティなら小さく試せる。そこで得た知見を社内に持ち帰って広げていく。これは私自身も「なるほど!」と膝を打った学びでした。
実際にスクラムフェスに参加してみて、そして今回のイベント運営にも関わってみて――「人とつながり、わいわい楽しむ」その体験こそが自分を大きく成長させてくれるし、私のモチベーションなんだと改めて実感しました。
人と話すのが大好きな私にとって、いつかは本格的にコミュニティの一員として支えながら楽しみたい!そう強く思えた楽しい時間でもありました。
BEMAも、エンジニアの皆さんがワクワクするような学びと交流の場を提供し続けられるよう、まずは私たち自身が楽しみながら活動していきたいと思います!
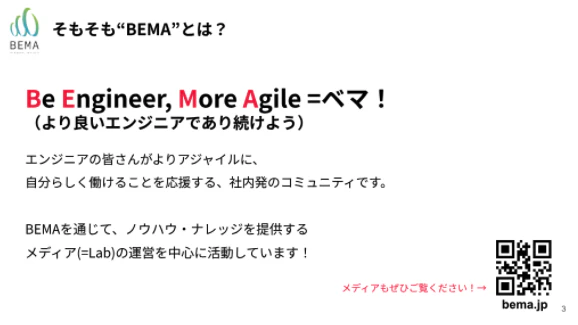
関連リンク
- BEMA Lab メディア: https://bema.jp/
- BEMA イベント: https://bema.connpass.com/
- BEMA Lab 公式X: https://x.com/BEMA_Lab
- 登壇者のXアカウント:
- 天野 祐介さん:https://x.com/ama_ch
- 小島 啓輔さん:https://x.com/prokoji18
- 天野 祐介さん:https://x.com/ama_ch
この記事を書いた人

関連記事
 【2025年11月版】人気記事ランキング|スクラム・キャリア...
【2025年11月版】人気記事ランキング|スクラム・キャリア...BEMALab 編集部
 『食べる』は距離を超える!リモート・異文化チームをつなぐ『食...
『食べる』は距離を超える!リモート・異文化チームをつなぐ『食...新岡 崚(ニイオカ)


What is BEMA!?
Be Engineer, More Agile








