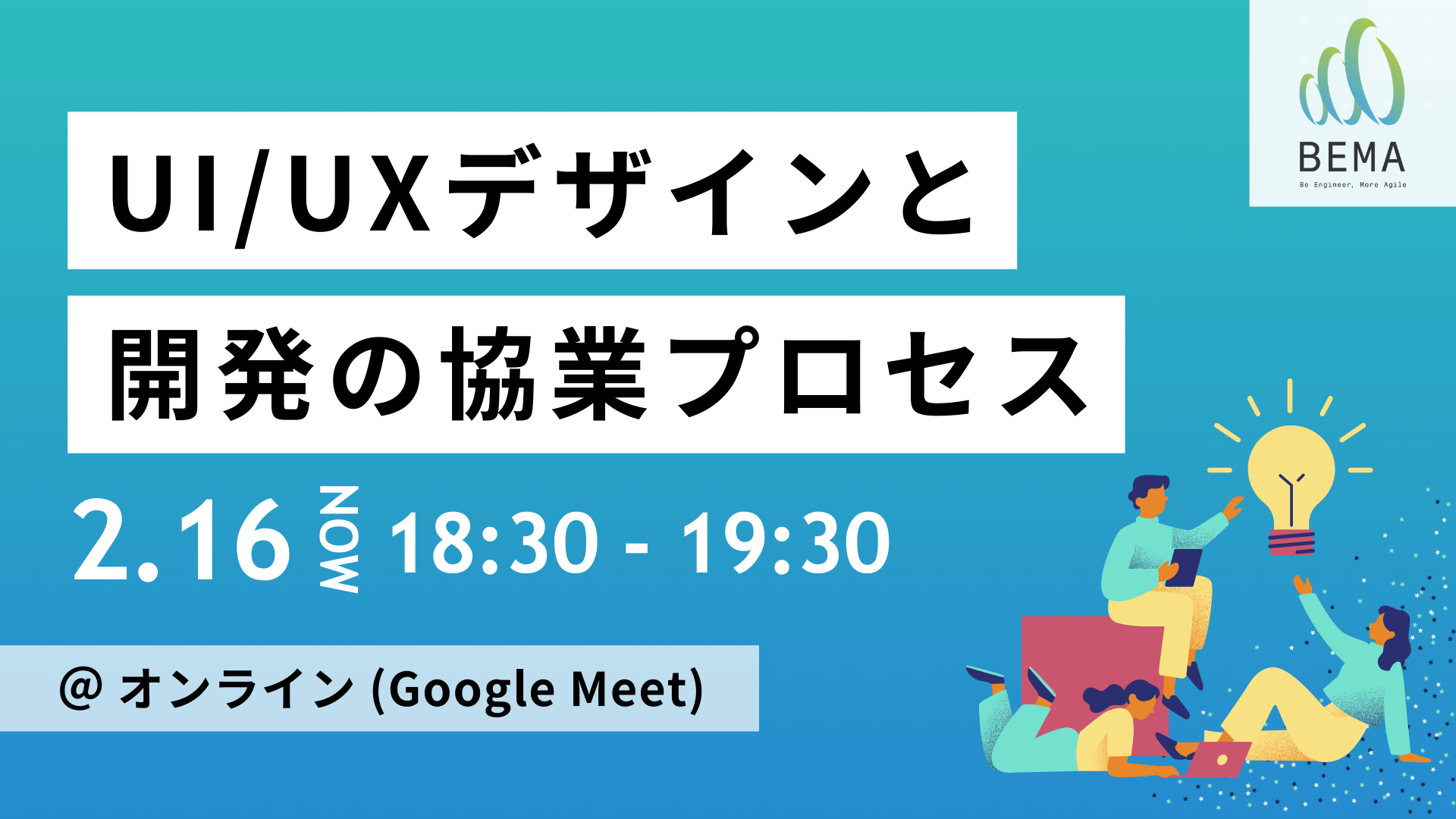【体験談】若手エンジニアが市場価値を高める3つの習慣|技術力不足を乗り越えるアジャイルなキャリア思考とは?
社会人1〜3年目のエンジニアの皆さん、こんにちは。株式会社メンバーズ エンジニアの兼子です。
エンジニアとして働き始めて約10年。私のキャリアはオンプレミスサーバーの導入支援から始まり、社内SE、システムコンサルティングといった幅広い業務を経て、現在は生成AI基盤の構築という最先端の領域に携わっています。
こうした多様な技術に触れる中で、私自身も若手時代には「自分の技術力は本当に通用するのだろうか」「この先どうキャリアを築けばいいのか」と、将来への不安や焦りを感じていました。もしかしたら、似たような思いを抱えている方もいるかもしれません。
本記事では、そんな私の10年間のキャリアを振り返り、若手時代に「これだけはやっておいて本当に良かった」と心から思う、自分の強みや得意領域を見極め、変化の早い技術業界でも柔軟にキャリアを築くための3つの習慣をご紹介します。
1. 「頑張った」だけでは伝わらない、成果を「数字」で語る習慣
日々の業務報告で、つい「頑張りました」「大変でした」といった定性的な言葉を使っていませんか?もちろん、その努力は素晴らしいものですが、それだけではあなたの貢献度や成果は、上司や同僚、そして自分自身でさえも正しく評価することができません。
若手時代から徹底して意識すべきなのは、自分の仕事の成果を常に「数字」で語ることです。
例えば、私が意識していたのは下記のような表現です。
「手作業で20人日かかっていたテストを、自動化によって1日で完了できるようにしました」
「2日を要していたサーバー構築プロセスを、スクリプト化して2時間で実行可能にしました」
数字は、誰が見ても揺るがない客観的な事実です。それはあなたの努力を可視化し、あなたの価値を最も雄弁に語る武器となります。
この習慣を身につける第一歩として、タスクに取り掛かる前に「このタスクでは、どのくらいの時間で、どのレベルの成果を期待されていますか?」と上司に確認することをお勧めします。これにより、自身の役割で求められる期待値が明確になり、目標設定の解像度が格段に上がります。
ここで身につけた定量的な評価能力は、将来的にプロジェクトの見積もり精度や計画策定能力に直結します。まずは、自分の仕事が生み出したインパクトを計測し、数字で語ることから始めてみてください。
2. 「Why(なぜ)」から始める思考法
目の前のタスクに追われると、私たちはどうしても「How(どうやるか)」という手段にばかり目が行きがちです。しかし、エンジニアとして本質的な価値を生み出すために本当に重要なのは、「Why(なぜこのタスクをやるのか)」という目的を深く理解することです。
以前、私が担当したシステム結合の自動化プロジェクトでの失敗談です。当初の私は、様々なツールを複雑に組み合わせる「How」に夢中になり、「とにかくすごい自動化の仕組みを作ること」が目的になっていました。しかし、プロジェクトの本来の目的、すなわち「Why」は「製品品質の向上」でした。
この目的を見失っていたため、私の作った仕組みは複雑すぎて、他のメンバーがテストコードを追加しにくいという本末転倒な結果を招いてしまったのです。
そこで私は一度立ち止まり、関連書籍を読み漁り、改めて「製品品質を向上させるための本質的な課題は何か?」を突き詰めました。その結果、本当に解決すべき問題は「いかにしてテストを作りやすくし、テストの実行数を増やすか」であることに気づきました。
アプローチを180度転換し、「自動で動くテストをいかに多く、簡単に準備できるか」に焦点を当てたシンプルな仕組みを再構築した結果、テストの抜け漏れが劇的に減少し、「製品品質の向上」という本来の目的を達成することができました。
この経験から、「Why」を深く掘り下げることが、技術選定の精度を高め、より本質的な解決策を導き出すのだと学びました。生成AIをはじめとするツールが進化し、効率化(How)が容易になった現代だからこそ、この「Why」を問う力が、技術に振り回されないエンジニアの核となるのです。
3. 食わず嫌いせず、多様な技術に触れる勇気
私のキャリアは、インフラエンジニアから始まり、社内SE、システムコンサルティングと、複数の職種を経験してきました。OSはLinux、Windows、Mac、クラウドはAWS、Google Cloud、Azureと、業界の主要なテクノロジーには一通り触れてきました。
これは、キャリア初期に与えられた機会に対して「これは自分の専門分野ではないから」と線を引かず、「食わず嫌い」をせずにすべて挑戦してきた結果です。
もちろん、すべてを完璧にマスターできたわけではありません。例えば、インフラの経験を活かしてバックエンド開発はある程度理解できましたが、フロントエンド開発は今でも苦手意識があり、自分でゼロから形にすることはできません。
しかし、この一見すると中途半端に思える挑戦こそが、私に大きな財産をもたらしました。それは、「自分自身の得意な領域と、そうでない領域の境界線を明確に知ることができた」という自己理解です。自分が本当に情熱を注げる分野がどこなのかを理解できたからこそ、自信を持ってインフラやAIという専門性を深めることができています。
若いうちは、あえて専門性を一つに絞らず、領域を広げることで自分の適性を見極め、将来のキャリアの選択肢を格段に広げることができます。
また、技術を磨くことと同じくらい重要なのが、社内外の人とのコミュニケーションを通じて多様な視座を身につけることです。技術を使ってシステムを作るのはエンジニアですが、そのシステムを使うのは「人」です。彼らが何を考え、何に困っているのかを理解する力は、AI時代にますます重要になります。幸い、このBEMA Labが発信拠点となっている株式会社メンバーズには、多様なバックグラウンドを持つエンジニアが集まっています。ぜひ積極的にコミュニケーションを取り、視野を広げてみてください。
まとめ
今回ご紹介した3つの習慣は、それぞれが独立しているようで、実は深く繋がっています。
「頑張った」だけでは伝わらない、成果を「数字」で語る習慣
「Why(なぜ)」から始める思考法
食わず嫌いせず、多様な技術に触れる勇気
これらは、エンジニアが不確実性の高い現代でしなやかに成長し続けるための、自分だけの「アジャイルなキャリア」を築くための基本要素です。
「数字」は、あなたの現在地を示し、次の一歩を改善するためのフィードバックループです。
「Why」は、あなたが進むべき方向を指し示すコンパスです。
「多様な技術への挑戦」は、最適なルートを見つけるために周囲の地形を把握する地図作りです。
社会人1〜3年目は、覚えることも多く、目の前の業務で手一杯になるかもしれません。しかし、皆さんが今向き合っている一つ一つのタスクが、間違いなく未来の皆さん自身を形作る重要なピースです。
焦らず、しかし着実に。この記事が、皆さんが自分らしいキャリアを築いていく上での一助となれば幸いです。応援しています。
What is BEMA!?
Be Engineer, More Agile