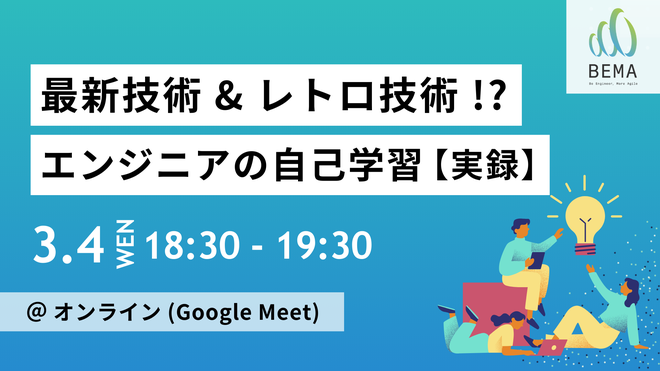アジャイルな「ふりかえり」の新しい手法。「チームドック」でチームの健康診断をしよう
miroで書いたチームドックの説明書
※こちらの画像作成にあたり、ふりかえりカタログ(コミュニティ版)のフォーマットを参考にさせていただきました!
はじめに
チームやプロダクトの状態を、健康診断のようにふりかえるフレームワークを作ってみました。
よかったら使ってみてください!(そしてフィードバックをください!)
どんな手法?
プロダクト・チームの状況を「人体」に例えて、健康診断のようにふりかえる「メタファーふりかえり」です。
「健康診断」のように定期的な実施を意図したフレームワークで、客観的/俯瞰的な視点でチームやプロダクトを眺める => 状況改善につなげられるのが特徴です。
進め方
簡単な「人体」をホワイトボードに描く。
体の部位(手や足などの他、胃、心臓などの内蔵)の付近に付箋を貼り、そこが今どういう状態になっているかを各自が書いていく。(どこが痛むのか、どこが好調なのか、違和感のある場所はどこなのかを「自己診断」するように)
付箋に書いた内容をチーム内で共有する
体全体をチームで俯瞰し、この人はどんな状態に見えるかを話し合う(風邪っぽい、今すぐ入院が必要、大怪我、大いに健康、など)
「(不調の場合)体の不調を解決するために何をするべきか、どんな治療法が考えられるか、不調の改善に必要なものは何か」「(生き生きとした体であれば)次に何をしたいか」などをチーム全員で話し合う
何が良い(と思って作った)手法なのか
<直感的で分かりやすいメタファー>
「体の健康」という誰にとっても身近でイメージしやすい題材によって、専門知識の有無にかかわらずチーム全員が参加しやすいふりかえり手法になっています。
<心理的安全性の高い場づくりに貢献>
メタファーを活用することで、本音が出しやすい場づくりが促進されます。
例えば、なかなか「プロセス・チームに問題がある」と直接的に指摘することは難しいですが、「胃の調子が悪い」といった比喩表現を使うことで、問題に言及する側の心理的ハードルを下げ、チームメンバーも個人攻撃やネガティブな話と捉えにくくなります。
<チームやプロダクトの全体感を共有できる>
個々の問題(付箋)だけでなく、「人体全体」を俯瞰して「この人(チーム・プロダクト)はどんな状態か」を議論することで、個別の事象の裏にある、全体的・根本的な課題やパターンに気づきやすくなります。
<ポジティブな側面にも触れられる>
「体の不調」だけでなく、「好調な部分」や「次に何をしたいか」にも目を向けることで、チームの強みや成長を再認識することができます。また、モチベーション向上や新しい挑戦にも繋がります。
活用方法のヒント
1.メタファーガイドを用意しておく
「どんな例えを書くか」が参加者の解釈に委ねられている自由さがこのフレームワークの良さですが、一方で「何をどう書いたらいいのか分からない」「議論が発散しすぎる」といった状況もよく起きます。
そのため、ファシリテーターは人体の各部位の「メタファーガイド」を用意しておくと、スムーズな「診断」に役立ちます。
【メタファーガイドの例】
頭(脳)🧠: チームの意思決定、計画、戦略、学習
目 👀: 顧客視点、集中、将来の見通し
耳 👂: ステークホルダーからのフィードバック、他チームとの連携
口 👄: コミュニケーション、情報発信、チーム内の発言量
心臓 ❤️: チームのモチベーション、情熱、プロダクトへの想い
胃腸 🌀: タスクの消化、プロセスの健全さ、情報の処理能力
手 ✋: アウトプットの質と量、具体的な作業、スキル
足 🦵: ベロシティ、開発のスピード、前進する力
背骨 🦴: チームの文化、原則、土台となるもの
免疫系/皮膚 ✨: 障害への対応力、問題からの回復力、外部からのプレッシャーへの耐性
これらの役割を最初に提示し、「例えば、口は『コミュニケーション』や『情報発信』を表しますが、皆さんの自由な解釈で貼っていただいても構いません」とアナウンスすることで、自由度と議論のしやすさを両立できると思います!
2. 「問いかけ」を工夫して多角的な視点を引き出す
付箋を書いたり、全体を眺める際に、ファシリテーターが「問い」を投げかけることで、より深く、多角的な意見を引き出すことができます。
例えば、以下のような感じです
不調 (痛み・違和感)
「ズキズキ痛む場所(=継続的な問題)はどこですか?」
「最近、急に痛くなった場所(=突発的な問題)はどこですか?」
「なんとなく重い、だるい場所(=言語化しにくい違和感)はどこですか?」
好調(エネルギー・成長)
「エネルギーがみなぎっている場所(=今のチームの強み)はどこですか?」
「最近、筋肉がついた(=成長・スキルアップした)と感じる場所はどこですか?」
「柔軟性が高まった(=変化に対応できた)と感じる場所はどこですか?」
全体: 変化と未来
「前回と比べて、良くなった/悪くなった場所はどこですか?」
「この体で『アスリート』を目指すなら、次に鍛えたい場所はどこですか?」
「診断」から「処方箋」への具体的な流れを作る
「風邪っぽい」「痛みがある」といった診断の後、対応策を「処方箋」として出すことで、ここでもメタファーのメリットを活用しつつチームのTryを出すことができます。
【処方箋のカテゴリ例】
薬の処方 💊: 新しいツールや技術の導入、ルール(薬の用法・用量)の策定
食事療法 🥗: 日々の仕事の進め方(デイリースクラムなど)の見直し、インプットする情報の質を高める
運動療法 💪: 新しいことへの挑戦、勉強会、スキルアップのためのトレーニング
休養 😴: タスクの棚卸し、技術的負債の返済、無理な計画の見直し
精密検査 🩺: 問題の根本原因を深掘りする (5つのWhy分析など)
専門医への相談 👨⚕️: 他のチームや専門家に助けを求める
ここでも、ファシリテーターが「私たちのチームの『胃もたれ』を治すために、どんな『処方箋』が考えられますか?」のように問いかけることで、具体的なアクションが出やすくなると思います!
終わりに
このふりかえり手法は、以下の「アジャイルと健康改善は同じ!」という動画を見たときに「そうじゃん!」と強く思ったその勢いで作りました。
なので、まだ私自身も試していません。ここから先はみなさんの目で確かめてください!
ただ、定期的に行うことで価値があるメタファーふりかえりとして、個人的に手応えがあります!
もしよかったらチームで試してみてください。使ってみた感想や改善点など、#BEMA Lab でX(Twitter)でのコメントでお待ちしています!よろしくお願いします!
この記事を書いた人

What is BEMA!?
Be Engineer, More Agile